今ある関係に感謝をし続け、今後も続く豊かな関係を
2022.08.16
2022.08.16
2022.06.24
羽田 優作
2022.06.10
羽田 優作
2022.05.27
羽田 優作
2022.05.20
2022.05.10
羽田 優作
2022.04.22
羽田 優作
2022.04.19
羽田 優作
周囲への感謝の気持ちを伝えることは、人間関係を豊かにし続けます。本記事では特に私が大切にする3つの考え方をお伝えします。読み終わった後にはつい照れてしまって感謝を大事な人に伝えきれていない人も「ありがとう」と周りに言いたくなるような記事です。
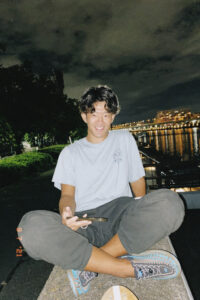
羽田 優作
2022年08月16日
長期的な関係を築く上では誰がしたかではなく「何をしたか」にフォーカスすることの重要性を学びました。学生団体など、日常生活において「誰がしたか」が注目されがちですが本質を見抜くことの重要性を学びました。
そして、支部長としていつも支部を支えてくれてありがとう。一緒に仕事をしている身としても非常に信頼もでき、これからもずっと応援したい人です。これからも頑張っていきましょう。
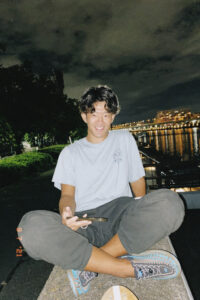
羽田 優作
2022年06月24日
■【Goal】本日の目標と計画の宣言(SMART+C)■
1.先週までの成果で、周囲の手本として伝えられること
・支部全体の方針を決めるプロジェクトを始動した中での動き方
・チームリーダーへのコーチング方法
2.来月の取組みで、周囲の手本として伝えられること
・支部全体の方針や注力業務を全体に伝達し、実際に動かすこと
3.本日、誰に対し、どのような価値を具体的に提供したいか
・同じ席になった仲間に対して、自身の強みである課題発見能力をいかし潜在的な課題を発見して指摘していく。
・同じ席になった仲間に対して支部単位での視座とチームやセクションでの視座を交えながらコーチングする。新たな気づきとそれぞれが抱えるメンバーの視座を挙げられるような具体策を提案していきたい。
■【Measure・Analyze・NextPlan】本日の振返り■
1.現状・成果の把握
・支部長セクションでやりたいこと、やるべきことを追っていただけでその後の定量・定性的なゴールとビジョンを描けていなかった。現状の課題を解決した先にある支部の未来と支部長セクションの理想像を描けていなかった。
・自分自身が伝わったと感じた情報でも伝わり方が異なることに気がついた。
2.ギャップの分析・課題の抽出
・発散と収束の思考を繰り返す、また対メンター、リーダー陣など多様なレイヤーに分けて考えることをあまりしていなかった。
・情報の発信など感情面が強く主張されており、具体性に欠けるものが多い事。
・視点の少なさ。今までは一人称視点でしかなく第三者視点を持ち多角的に捉えることができていなかった。
3.今後の対策・計画
・セクション内で話を完結させない。扱っている議題や課題は支部に関わる重要なものが多い。100名近いメンバーがいる支部だからこそ多角的な意見や情報を取りにいく姿勢を体現する
・支部長セクション内の個人の役割を明確にする。自分が持つ期待と役割と相手が思う適性を擦り合わせ最適化を図る
・行動するより前にゴールとビジョンを固める。そうする事でその行動に妥当性を持たせる。
■【周囲への感謝】リーダーやコーチに具体的に感謝したいこと■
誰から、どのような価値を頂きましたか。(感謝の気持ちも一緒に)
※最も潜在ニーズにアプローチし、必要であれば耳の痛いこともアドバイスしてくれたメンバーには名前の前に◎をつけてください。(1人のみ)
谷風花さん◎
「ブラックボックス化を解消した先に支部長セクションがどう思われたいの?」という質問が本質的で考えるきっかけになりました。本気で思いをぶつけつつ、課題をしっかり見抜いていただき勝ちをいただくことができました。ありがとうございました。
久野滉大さん
課題の指摘だけでなく、感情をしっかり伝えていただきアドバイスだけでなく応援をしてくれました。率直な質問をぶつけてくれることのありがたみを感じました。ありがとうございました。
川村杏さん
現状ある支部課題をODセクションリーダーとして共有してくれるだけではなく共に解決していくパートナーであるというメッセージをいただいたような気がしました。ありがとうございました。
本日の研修を共に価値のあるものにしていただきありがとうございます。この研修とディスカッションの中で私が気づかなかった問題点を指摘していただくことができ、非常に有意義な時間となり具体的な施策に落とし込むことができました。次は指摘されないように先回りして動くことを徹底します。
復習回数を闇雲に増やしたり、ノートいっぱいに何度も書かせる記憶法は、社会に出てから通用しない。 多忙なリーダーは、重要事項を一発で覚える。 たとえそれができなくても、復習回数を最小限にし、効果的・効率的に記憶することが大切。
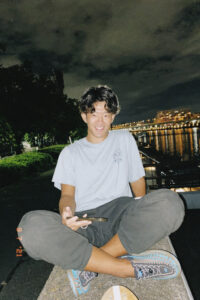
羽田 優作
2022年06月10日
■研修を受けて■
記憶には種類があり、そこにはメカニズムがあることを初めて知ることができました。これまでの研修でも体感していましたが、何事も機能面の違いを活用していくことが大事だと思いました。復習する機会と適切な頻度や記憶の種類を掛け合わせることで最大化できるようになると思いました。
また、記憶という身近な話題ですが参加者の方とディスカッションすると全く異なる観点や気づきを得ることができ、自身の成長につながると確信しました。
■今後に向けて■
今後は「どのように記憶してもらうか」を意識していこうと考えます。相手の欲求にアプローチしつつ、エピソード記憶と意味記憶の適切なバランスを個人単位で調整して最適化していくことが、現在の活動において重要かつ最も効果的であると考えました。小さなことを着実に、日々の生活の中でアウトプットしていきます。
■研修講師(森口敦)へのメッセージ ■
本日は、貴重なお時間をいただきありがとございました。研修の内容は毎回興味深くかつ本質的で、これまでの活動と今後の活動について考えるきっかけになっています。その中で今回の研修では、記憶のメカニズムを活用することで変数を最大化できるということを自分なりに考えました。このようなきっかけを頂くことができて大変感謝しております。今後ともよろしくお願いします。
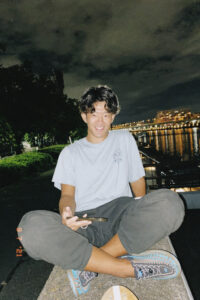
羽田 優作
2022年05月27日
■【Goal】本日の目標と計画の宣言(SMART+C)■
1.先週までの成果で、周囲の手本として伝えられること
・プロジェクトに入り込んだ際に、どのようにして短期間で周囲のメンバーを巻き込み円滑に動かしていくか
・そのプロジェクトをどのようにして支部全体に浸透させていくのか
2.来月の取組みで、周囲の手本として伝えられること
・ビジョンを明確にしつつ、短期・中期・長期の計画を立てる重要性
・プロジェクトやセクション業務に対して支部全体を巻き込んでいく方法
・コミュニティの側面を担保しつつ、チーム単位で目標数値を追っていく姿勢と方法
・支部長セクションとして、エンカレッジ早稲田支部の中での自身の責任権限義務の整理
3.本日、誰に対し、どのような価値を具体的に提供したいか
・リーダー達に、支部に対して与えて欲しいインパクトを伝えること。業務内容だけではなく、背景から具体的な方法、設定して欲しい目標を基準化数値化して伝え擦り合わせる
・リーダー達が課題だと思っていない箇所に対する指摘を支部というメタな視点から俯瞰し、解決案を提示していく
■【Measure・Analyze・NextPlan】本日の振返り■
1.現状・成果の把握
・数値での達成、組織の人数と組織体制を把握
・現状立てていた計画とその乖離を数値面とソフト面から分析した
2.ギャップの分析・課題の抽出
・年間計画を立てる上で必要な情報の定義が曖昧
・注力事業やセクションを決定できていない
・事業としての成功と組織としてのゴールを並走させる
3.今後の対策・計画
・支部の年間計画を立てる上で必要な情報の定義づけ、回収
・止血する場所と伸ばす場所を定義する
・ミニマムか支部全体か、併用かを考える
・時間軸での注力セクションの決定とその後の支部の年間ストーリーを決める
・支部へ周知(7月総会が理想)
■【周囲への感謝】リーダーやコーチに具体的に感謝したいこと■
誰から、どのような価値を頂きましたか。(感謝の気持ちも一緒に)
※最も潜在ニーズにアプローチし、必要であれば耳の痛いこともアドバイスしてくれたメンバーには名前の前に◎をつけてください。(1人のみ)
須賀さん◎
本田さん
平山さん
本日はありがとうございました。特に計画を立てる上での抑えるべきポイントとNPOとしてのあり方を経験や考えから学ぶことができました。特に月毎の主役を決める方法がクリアになりました。ありがとうございます。
報告・連絡・相談。 言葉だけを知っていても意味がない。 報告・連絡・相談の違いと「判断力・決断力」の関係 報告・連絡・相談のタイミングと「マネジメント・人材育成」の関係 これらを理解し、効果的に使い分けることが重要。 理屈と機能を理解することでチームワークが大きく向上したいリーダーのための研修です。
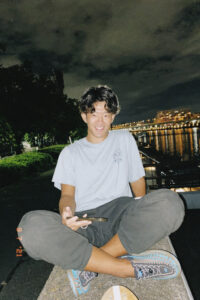
羽田 優作
2022年05月10日
■研修を受けて■
・本日の研修では「責任」「権限」「義務」と「報告」「連絡」「相談」には体系的な繋がりがあることを学ぶ事ができました。リーダーとして、部下や仲間を人材から人財へ成長させるためには、この要素のつながりを意識することで成長速度とプロジェクトの進捗の速度が格段に上がることを学びました。そして、自分本位の「報告」「連絡」「相談」をするのではなく、自分たちが行うことには全て相手がいることを意識することで、相手本位のコミュニケーションが取れると感じました。
■今後に向けて■
今後は、「責任」「権限」「義務」を明確にすることを第一にします。そこで明確になったものを「報告」「連絡」「相談」に関するグラウンドルールを設定することで円滑かつ効果的なコミュニケーションを取る土台を作成します。そして、自分が関わるエンター、メンター、支部長などに対してのそれぞれのルールや共通認識を構造化して考えることで具体に落とし込み、限られた時間で効果的なコミュニケーションを取ることを意識します。
■研修講師(森口敦)へのメッセージ ■
森口さん、本日も貴重なお話を聞かせてくださりありがとうございました。以前「コミュニケーションは仕事を豊かにする」と学びましたが、ビジネスにおけるコミュニケーションは「報告」「連絡」「相談」がコミュニケーションだと学びました。
本田さん、リーダーとしてありがとうございました。私自身が課題であると認識しているものに対して多角的な指摘をいただく事ができました。また、時間を有効活用したチームでのコミュニケーションを常に意識してくださり効果的なディスカッションができるようになりました。
本日も、ありがとうございました。実践していこうと思います。
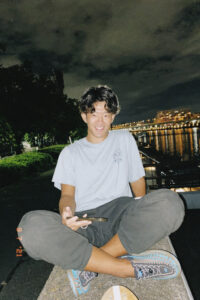
羽田 優作
2022年04月22日
■【Goal】本日の目標と計画の宣言(SMART+C)■
・以前の研修で発見できた自身の強みと弱みを活用し、支部長セクションとしての目的・目標と責任・権限・義務を明文化し、セクションの意義を再把握し個人・セクション単位での定量的な年間計画と定性的な目標を設定する。
・各報告項目で1つ以上気づきを発信する
・以前の研修で気付いた「行動が思考先行する癖」を一度も出さず、自分自身が納得するまで質問をして、相手に新しい気づきを一個でも多く提供することで研修を作り上げていく。
・自分自身と研修を作り上げていく仲間と運営スタッフ、森口さんに誠実に向き合い続ける。
■【Measure・Analyze・NextPlan】本日の振返り■
1.現状・成果の把握
・支部長セクションの責任・権限・義務を明確にできた。
・定量的な年間目標まで落とし込めた。
・各項目で1個以上の気づきを発するコーチングができた。
・自分や研修に参加している仲間と誠実に向き合えた。
2.ギャップの分析・課題の抽出
・リーダー育成や成長機会提示の機会創出システムが考えられていないところ。
・「システムをつくる」という観点が研修参加前の自分自身にない部分であった。
3.今後の対策・計画
・支部長セクションとしてあらゆる業務を「システムの中に落とし込む」観点で再定義していく。
・自身がセクションに提供できる価値を再定義し、メンバーとの期待とすり合わせて具体的な業務内容まで落とし込む。
■【周囲への感謝】リーダーやコーチに具体的に感謝したいこと■
1.誰から、どのような価値を頂きましたか。(感謝の気持ちも一緒に)
※最も潜在ニーズにアプローチし、必要であれば耳の痛いこともアドバイスしてくれたメンバーには名前の前に◎をつけてください。(1人のみ)
◎小黒さん
コーチングの際に、業務プランについての深掘りの観点が鋭く、仕組み作りだけではなく大枠の構造を変えることも視野に入れながら考えることが重要だと気付かされました。ありがとうございました。
川村さん
支部長セクションの年間計画の活動内容とミッションの漏れを指摘していただき重要な部分が欠けていた事を把握することができました。ありがとうございました。
単なる就業体験では意味がない。 単なる発表会でも意味がない。 参加者の能力開発にこだわった集中プログラム。 今のうちに自身の限界にチャレンジし、社会で役立つ自身の強みを見つけ、今後の学生生活や就職活動に大いに役立ててほしい。 机上の空論で終わらせない、責任あるリーダーのための特別プログラムです。
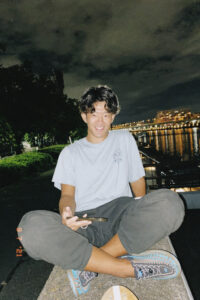
羽田 優作
2022年04月19日
■研修を通じて学んだこと■
・コミュニケーションは仕事を豊かにする
・まず概念化して話す
・基準化と数値化をする重要性
・リーダーとしてメンバーの人生を預かっている自覚を持つ
・リーダーこそが自身の弱みに向き合う重要性
・説得力の高い意見に従う
・自身と信頼の積み重ねのメカニズム
・限られた時間をいただいているという意識を常に持つ
・常に本質を見抜く
・リーダーとしてのノルマとコミットメントの使い分け
・何事も知恵を使って取り組む
・「責任」「権限」「義務」の違い
■研修を通じて気付けたこと、今後に役立てられること■
・常に自身の弱みに向き合うこと
私はこれまで自身の弱みに目を背け、かつ気付いているふりをしていたことを痛感しました。自身の弱みに誠実に向き合う事は精神的な負荷になることを知っており、それを本能的に逃げていたのかもしれません。しかし、リーダーとしてメンバーやエンターなどと真摯に向き合う上で自身の弱みと向きあう事で自分自身だけではなくメンバーの成長を促すことができると確信しました。そして、弱みに向き合うからこそ、その弱みを改善するために日頃の生活から心がける事ができると感じました。私はこの研修の中で自分自身の弱みと’誠実に向き合えたからこそ成長できると確信する事ができました。
・指摘をラッキーだと思うこと
研修は参加するものではなく、参加者と主催者と共に作り上げるものです。その上で、自身の弱みや癖を指摘していただける機会というのは実は「貴重」であるのだと確信しました。だからこそ、自分自身の弱みや癖を指摘していただいた時こそ自分自身の成長の余白だと捉え積極的に修正しようと心がけました。受動的ではなく能動的に働きかけることが大事だと考え、このマインドを持って常に相手に真摯に向き合うことの重要性を学びました。
・ギリギリを狙わない
何事もギリギリを狙わない事は、実は意識しないと難しい事だと意感じました。人間は怠ける生き物です。何事にも圧倒的な準備をすることこそ、してと誠実に向き合う準備ができると考えます。従って、ギリギリを狙わないマインドセットを持たなければ相手や自分自身と誠実に向き合うことができないと痛感しました。特にメンバーを背負うリーダーや、相手がいるビジネスの場においてギリギリを狙うこと自体が失礼に値するという事も同時に学ぶことができました。
■研修参加前後での心境の変化、研修講師やA&PROメンバーへのメッセージ■
まず、本研修を運営してくださった森口さん、その他の運営メンバーの皆さん本当にありがとうございました。また、参加していたメンバーの皆さんも一緒に学びの多い研修を作り上げてくださりありがとうございました。研修中の全てが学びであり価値のある時間を共に過ごすことができました。
研修前までは「リーダー」という存在や定義をあまり考えたことがありませんでした。しかし、「リーダーは準備ができている人がやる」という当たり前ではありますが本質的なことに改めて気付かされました。だからこそ私が所属する団体の中で皆から信頼されるリーダーになる準備とそれに必要な素養を学ことができました。そして、自分自身の本当の弱みに向き合ったからこそ相手に誠実さを持って接することができると感じました。これからは自分自身に足りない部分を補いながら、信頼されるリーダーになる準備を入念に行おうと考えるようになりました。
■これからリーダーシップゼミを受ける人へのメッセージ■
この研修はこれまでリーダー経験が豊富でも、そうではなくても参加するべき研修であると考えます。おそらくほとんどの人が「リーダーとは何か」という問に対する答えを見つけられていないと思います。自分自身が考えるリーダー像と、本当に信頼されるリーダー像では乖離があると思います。そして、リーダーではなくても「誠実さ」とは何かを学べる貴重な機会です。自分自身の成長と、自分に関わる全ての人の成長を促進できる重要な要素を学べる機会です。ぜひ積極的に、能動的に参加して欲しいと思います。
■推薦してくれた方へのメッセージ■
私を推薦してくださった山田飛翔さんと白石知朗さん、誠にありがとうございます。この研修に参加したからこそ自分自身の「未熟な弱さ」に気づく事ができました。リーダーとして日々の鍛錬を怠らないことの重要さや、本当の意味で信頼されるリーダーになる覚悟を醸成する事ができました。この経験を単発で終わらせる事なく日々の生活や活動の中で積極的に鍛錬して、より信頼されるリーダーになろうと強く決心する事ができました。
2022.05.20
まだフォローしていません
人は何に対して導かれるのか、そのメカニズムについて体系的に研究。①パワー理論②信頼残高③影響力の武器 自分の欲求で相手に働きかけるのではなく、相…
人が自ら動きたくなる組織には、「信頼」「理解」「成長支援」の3つの要素があります。 本研修では、マグレガーのXY理論・マズローの欲求5段階・コーチングの領域モデルを用いて、 「人はなぜ動くのか」「どうすれば自ら動くようになるのか」を、実例を交えて深く学びます。 単なる知識の習得にとどまらず、現場で直面する課題(メンバーの停滞・生徒の伸び悩み・顧客対応の難航など)を、“人間理解”を通して紐解く実践型のプログラムです。
人が自ら動きたくなる組織には、「信頼」「理解」「成長支援」の3つの要素があります。 本研修では、マグレガーのXY理論・マズローの欲求5段階・コーチングの領域モデルを用いて、 「人はなぜ動くのか」「どうすれば自ら動くようになるのか」を、実例を交えて深く学びます。 単なる知識の習得にとどまらず、現場で直面する課題(メンバーの停滞・生徒の伸び悩み・顧客対応の難航など)を、“人間理解”を通して紐解く実践型のプログラムです。
玉井 人生100年時代といわれる今、私たちが「自身にとって最もよい人生を送る」ためには、健康や医療に関する情報を正しく判断し、適切な選択や行動を…
人が自ら動きたくなる組織には、「信頼」「理解」「成長支援」の3つの要素があります。 本研修では、マグレガーのXY理論・マズローの欲求5段階・コーチングの領域モデルを用いて、 「人はなぜ動くのか」「どうすれば自ら動くようになるのか」を、実例を交えて深く学びます。 単なる知識の習得にとどまらず、現場で直面する課題(メンバーの停滞・生徒の伸び悩み・顧客対応の難航など)を、“人間理解”を通して紐解く実践型のプログラムです。
コンサルタント・コーチ・メンター、政治家・医師・経営者、そしてチームリーダー。A&PROが関わる相手の多くが、自らの存在や組織をブランド…
この記事がNewsPicksの【キャリア・教育】【注目のトピックス記事】で紹介され、話題になっています。 本記事は、渾身の企画やメッセージがなぜ…
『責任を持つ』とは、起こりうることを想定し、想定外にも対応できる状態でいること。メンバーと顧客の生命を、机上の空論でなく、本気で守るリーダのため…
理論や蓄積されたノウハウ、他者の意見を取り入れず、自分のこれまでの経験や能力に頼りすぎて、失敗した経験はないでしょうか。自己流を脱却し、周囲を巻き込みながら組織の成果に貢献する方法をお伝えします。
責任・権限・義務。 言葉だけを知っていても意味がない。 責任・権限・義務の違いと互いの関係 報告・連絡・相談の違いと「判断・決断」との関係 報告・連絡・相談のタイミングと「マネジメント・人材育成」の関係 これらを理解し、効果的に使い分けることが重要。 理屈と機能を理解し、チームワークを大きく向上したいリーダーのための研修です。
感謝は大事だと分かっているけれど、感謝を後回しにしてしまう。そんな方に、感謝の価値を改めて実感していただき、実践するための準備となるメッセージになればと思います。
コンサルタント・コーチ・メンター、政治家・医師・経営者、そしてチームリーダー。A&PROが関わる相手の多くが、自らの存在や組織をブランド…
人間力・仕事力を高めるWEB chichiの、「地球上で最も必死に考えている人にアイデアの神様は降りてくる」<ジャングリア沖縄の仕掛け人・森岡毅…
復習回数を闇雲に増やしたり、ノートいっぱいに何度も書かせる記憶法は、社会に出てから通用しない。 多忙なリーダーは、重要事項を一発で覚える。 たとえそれができなくても、復習回数を最小限にし、効果的・効率的に記憶することが大切。
窪田:中室先生はご著書『科学的根拠(エビデンス)で子育て』の中で、エビデンスを重視した教育の必要性を説いていらっしゃいます。そもそも金融業界にい…
クレド7.好奇心旺盛、常に学ぶ。 我々の活動における身近な事柄に興味を持ち、深く学ぶ事を大切にしていきます。教え上手は当たり前、学び上手であれ。…
コンサルタント・コーチ・メンター、政治家・医師・経営者、そしてチームリーダー。A&PROが関わる相手の多くが無形サービスを中心に活躍して…
コンサルタント・コーチ・メンター、政治家・医師・経営者、そしてチームリーダー。A&PROが関わる相手の多くが無形サービスを中心に活躍して…
顧客に新しい価値を創造し続けるためには自らの脅威と向き合い、あえて自社の優位性を覆していくようなサービス・プロダクト開発が必要です。
知識として体系化されているプロジェクトマネジメント。 ただし、頭で理解していても習慣化できていないと、顧客やステークホルダーの期待値とは程遠い『自己満足なプロジェクト』となってしまう。
新規登録
アカウントをお持ちの場合はログインする
羽田 優作 早稲田大学