自ら道を創り、仲間と道を切り拓き、事業と組織を進化させる
2023.04.03
2023.04.03
2023.03.10
香山 渉
2023.03.06
2023.03.03
2023.02.24
香山 渉
2023.02.10
香山 渉
2023.01.29
2023.01.27
香山 渉
2023.01.10
香山 渉
2023.01.07
2023.01.07
2023.01.07
2023.01.07
2023.01.07
2023.01.07
2023.01.07
2023.01.07
2023.01.07
2022.12.16
香山 渉
2022.12.10
香山 渉
2022.11.11
2022.11.10
香山 渉
2022.10.21
香山 渉
2022.10.18
2022.10.05
2022.09.26
2022.09.23
2022.09.23
2022.09.23
2022.09.23
香山 渉
2022.09.10
香山 渉
2022.08.27
2022.08.26
香山 渉
2022.08.15
2022.08.14
2022.08.10
香山 渉
2022.07.22
香山 渉
2022.07.10
香山 渉
2022.06.24
香山 渉
2022.06.10
香山 渉
2022.05.27
香山 渉
2022.05.10
香山 渉
2022.04.22
香山 渉
2022.04.10
香山 渉
2022.01.07
2021.12.20
香山 渉
尊敬できる方と出会い、素敵な関係性に溢れた大学4年時。一方でもどかしさを抱え続けた時期もありました。その差の正体を分析し、豊かな人生を歩むコツをお伝えします。そして、事業・組織・社会を創る人財として成長を見据え、社会人としての行動指針を綴ります。
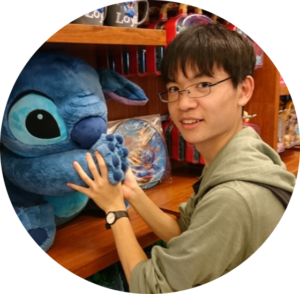
香山 渉
2023年04月03日
須賀さんの大学生活の集大成とも言えるような記事で、最初から最後まで須賀さんの学生生活を想像しながら追体験することができました。
支部長として,組織のために考え抜いていてくださったからこそ,今のエンカレッジ早稲田支部が存続し,エンターへの価値提供を継続できているのだと思います.
須賀さんの4つの行動指針を読み、私自身も誠実に謙虚に、かつ主体的に生きる人財になろうと強く思いました。
人は何に対して導かれるのか、そのメカニズムについて体系的に研究。①パワー理論②信頼残高③影響力の武器 自分の欲求で相手に働きかけるのではなく、相…
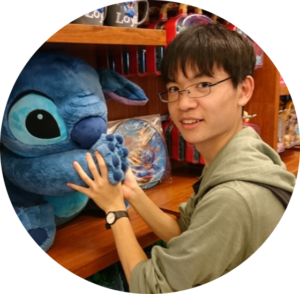
香山 渉
2023年03月10日
■研修を受けて■
・依存関係が生じた際に人は他人から影響を受ける
・人からの信頼は,自分が当人にしてきた行動から判断できる(信頼残高)
・6つの影響力の武器
→返報性の原理
→コミットメントと一貫性
→社会的証明
→好意
→権威
→希少性
■今後に向けて■
・人に何かしてほしい際には,まず当人の成熟度と欲求段階を把握する必要がある.自身の経験と価値だけで判断せずに,当人の過去の経験や大切にしている価値観にまで踏み込んでコミュニケーションをとることにより,豊かな成果に結びつけることができると感じた.社会人として,周囲の人と仕事する際には彼ら彼女らが見せていない一面にまで知ろうとする姿勢を持っていきたい.
・6つの影響力の武器を知ったからこそ,誠実に周囲の人に対して向き合うことを怠らずにしたい.自身の消費者としての経験から,戦略的なものは必ず見透かされると感じているため,社会人としてクライアントや同僚,上司と部下に対して誠実な関心を向け,一貫性を持った行動を心がけていきたい.
■研修講師(森口敦)へのメッセージ ■
1年間にわたりご指導いただきましてありがとうございます.本日研修では,過去1年間の森口さんの言行を振り返り,影響を与えていただく工夫をしていただけたことに気づきました.今後は社会人として働くにあたって,周囲の見本となるような人財になるべく,日々勉強を続けて参ります.改めて御礼申し上げます.
コミュニケーションはあらゆる分野で成功したり、人生を豊かにする基礎スキルであり、コミュニケーションを学ぶことは人生の可能性を大きく広げるのではないでしょうか。自分本位の人間関係を脱却し、豊かな人間関係を構築したい方にお薦めの記事です。
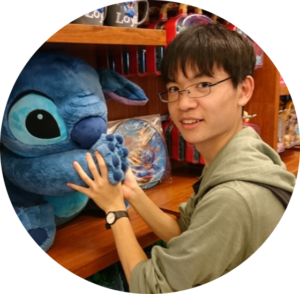
香山 渉
2023年03月06日
"""
経験則ももちろん大事ですが、理論の学習を進め、再現性を高め、相手の「真」の姿を理解できるように日々努力したいと思います。
"""
まさに、守破離の"守"に相当する部分だと感じ、自己流に拘りすぎないために必要な考え方だと思いました。
仕事を決めるとき、何を基準にしていますか?学生のアルバイトであれば、時給や仕事場の近さで決めているかもしれせん。若いからこそ、多くの時間を費やす仕事には大きなチャンスが存在します。本当に価値のある仕事とはどのようなものでしょうか?
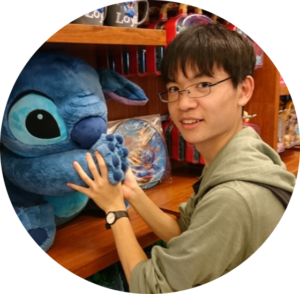
香山 渉
2023年03月03日
私自身も研究をしていることもあって、興味深くかつ学び多く読ませていただきました。
適切な目的と、中長期的な視野を持って、大変なことに自分も取り組みたいと思います。
リーダーシップゼミやビジネス基礎研修で学んだことを、机上の空論とせずに実践し続けることが重要。 プロジェクト年間計画をもとに毎月、リーダー同士でチームコーチングを実施します。 ※参加者同士で役割分担し運営する研修です。
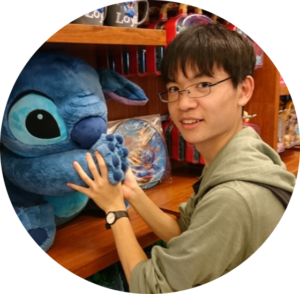
香山 渉
2023年02月24日
■【Goal】本日の目標と計画の宣言(SMART+C)■
1.先月・先週までの成果で、周囲の手本として伝えられること
・11期のスタンスを高めることに先立ち,引継ぎの一環で「これをしてほしい」ではなく「問い」として投げかけること。
・組織の解散に先立ち、これまでの活動から悔いなく終えられるためにメンバーへの問いかけ
2.来月の取組み/残りの活動で、周囲の手本として伝えられること
・11期のスタンス醸成とそれに並行した自身の社会人になる前の準備.
・先の「問い」をメンバー間で共有し,思考してもらうことによる引継ぎの事例.
3.本日、誰に対し、どのような価値を具体的に提供したいか
1年間リーダーとして並走してきたメンバーに対して,これまでの活動で振り返りきれていなかった当人の強みと弱みを言語化し,社会人としての期待を伝え,活力高く4月を迎えるコーチングをしていきたい。
山口さんに対して,11期の組織を牽引する立場として,人を動かしていくために自身の思いやわくわくする目標を掲げることの重要性を,自身の5月頃の経験を基に伝えていきたい.
■【Measure・Analyze・NextPlan】本日の振返り■
1.現状・成果の把握
・1年間の活動を振り返ると共に,自身の発揮してきた強みと今だに克服できていない弱みの双方について言語化することができた.
・併せて,10期MPとして提供してきた価値の背景の自身のどんな取り組みがあるのかを評価することができた.
・久野さんへのコーチングにおいては,当人の小さな頑張りにも目を向け,感謝と尊敬の念を伝えることができた.
2.ギャップの分析・課題の抽出
・自身の活動を客観的に振り返り,弱みに向き合おうとする姿勢が言語化に繋がったのではないか.
・言葉一つ一つに耳を傾けつつ,自身が活動する中で気づいた久野さんの頑張りを自分主語で伝えることができたのでは.
3.今後の対策・計画
自身の行動を定期的に振り返るにあたって,他者からどのように見えていたのかをフラットに受け止めることに加えて,自分自身が強みと弱みに向き合う姿勢を持つことが必要.
■今後社会人・リーダーとして、今後も克服していきたい課題もしくは大切にしていきたいことは何か■
・組織の課題を自分事化し,自身の変数としてできることを行動し続けることを大切にしたい
・課題に向き合い続けるために,その課題に対して関心を持ち続け行動し続けることを大切にしたい
・自身の持つ情報が古くならないように,常にアンテナを張って情報を収集し続けることを大切にしていきたい
■【周囲への感謝】リーダーやコーチに具体的に感謝したいこと■
誰から、どのような価値を頂きましたか。(感謝の気持ちも一緒に)
※最も潜在ニーズにアプローチし、必要であれば耳の痛いこともアドバイスしてくれたメンバーには名前の前に◎をつけてください。(1人のみ)
◎久野さん
11期へのMPの引継ぎに関する部分で,10期の思いを如何に11期に伝えていくかの助言をいただきました.当に迷っている部分でしたので,久野さんの実践してきたことを自身も実践していきたいと思います.ありがとうございます.
〇本田さん
自身の弱みに直で向き合っていただき,どのようにすれば克服するきっかけとなるかの指針を気づかせていただきました.ありがとうございます.
「マグレガーのXY理論」「マズローの欲求5段階」「コーチングの領域」を身近な具体例で深掘りし、コーチングの実践に役立てる。 現場の活動と有機的に結びつける知恵と、今後のプロジェクトに活かす行動力。 これらを大切にするリーダーのための研修です。
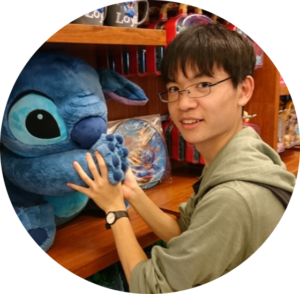
香山 渉
2023年02月10日
■研修を受けて■
・マグレガーのXY理論
→X理論は命令や強制によってされるもの
→Y理論はメンバーの自発的な行動によるもの
・マズローの欲求5段階
→生存欲求から自己実現欲求まで,欲求の段階によってクライアントに提案する内容やかける言葉が変わってくること
・コーチング実践の場
→目的目標を明確にしないことにはコーチング以前に的外れな提案をしてしまう可能性があることを学んだ
→相手の目的目標を明確にし,できる瞬間できない瞬間を明確にすることで原因を突き止めることができること
■今後に向けて■
・エンカレッジの活動でメンバーをマネジメントする立場として,メンバーにとっての欲求の段階がどこにあるのかを把握することが先決であると感じた.欲求段階が不明瞭である状況での適切な提案や相談を受けることが不可能に近いと,本日のコーチングを実践して感じた.
・クライアントに向けてだけではなく,自身を律する意味でも,自分ができるときできないときを振り返ることで,本来目指す理想の状態を目指していきたい.具体的には,朝早く起きるための環境づくりや,日々の自己研鑽をするきっかけを用意しておくことをやっていきたい.
■研修講師(森口敦)へのメッセージ ■
本日も貴重なお時間をいただきましてありがとうございます.本日の研修を通じて,自身のコーチングの癖を把握することができた他,直近の自身の悩みに対してどのように向き合うべきかを考えることができました.
理論や蓄積されたノウハウ、他者の意見を取り入れず、自分のこれまでの経験や能力に頼りすぎて、失敗した経験はないでしょうか。自己流を脱却し、周囲を巻き込みながら組織の成果に貢献する方法をお伝えします。
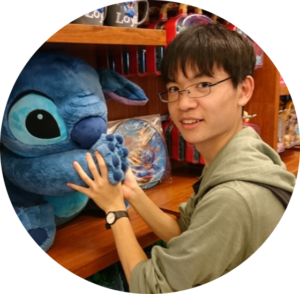
香山 渉
2023年01月29日
自己流から抜け出し、本来の目的に立ち返ることの大切さを学んだと同時に、その難しさを推し量ることができました。
今11期が立ち上げを遂行できているのは、須賀さんの努力の積み重ねと、かけてきた時間があるからこそのものだと強く感じました。改めてありがとうございます。
リーダーシップゼミやビジネス基礎研修で学んだことを、机上の空論とせずに実践し続けることが重要。 プロジェクト年間計画をもとに毎月、リーダー同士でチームコーチングを実施します。 ※参加者同士で役割分担し運営する研修です。
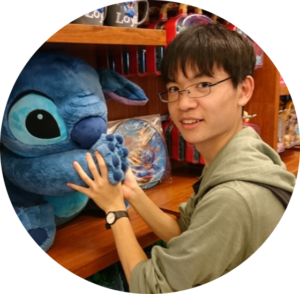
香山 渉
2023年01月27日
■【Goal】本日の目標と計画の宣言(SMART+C)■
1.先月・先週までの成果で、周囲の手本として伝えられること
ゴールから逆算するという観点で、特にOJT終了時の11期の心境と想定アクションまで明確に言語化したこと
→ 目標達成に向けて何が必要かの明確化、メンバーへの準備を促すことができた
2.来月の取組みで、周囲の手本として伝えられること
・エンカレッジ卒業後を見据えたセクションメンバーのボンド形成の取り組み
・1年間の活動の振り返りと、OJTを通して得た引き継ぐ上での言葉選びや伝え方
3.本日、誰に対し、どのような価値を具体的に提供したいか
・谷さん
同じセクションのメンバーとして、現在行っている施策を効果あるものとするための観点を1つ提供したい。
卒業後のボンド形成にあたってもMPとしてどうかかわっていきたいかの提案をしたい。
・久野さん
11期への引継ぎにあたって、9期からの情報の受け取るタイミングや媒体で感じた自身の立ち上げ時の経験を伝えながら、手段を1つ提供していきたい
・11期 吉川さん
獲得戦略を立てるセクションとして、他セクションとの連携の可能性に気づいてもらい、支部全体で獲得する示唆を与えたい
■【Measure・Analyze・NextPlan】本日の振返り■
1.現状・成果の把握
〇メンバーへのコーチングに関して
大方達成できたのではと感じている(コラム周りの相談をしたこともあり、MPのボンド形成の話はできなかった)。
〇自身のプロジェクトの振り返り
11期への引継ぎにあたっての内容やスケジュールを客観的に見直すきっかけとなった。
OJTの期間の細かいスケジューリングが的確にできていなかったこと。
また10期メンバーへの責任権限の分配が適切でなかったことが判明した。
2.ギャップの分析・課題の抽出
先にOJTを実施しているSLの振り返りを聞くことで初めて、MP-OJTとして備えなければならないことが浮上してきた。
また、自身が11期に伝えたいことが先行していたときにつくった仕組みのまま引継ぎを始めることになっていたことが、責任権限の分配ができていなかったことの要因ではないか。
3.今後の対策・計画
OCやEVのOJTの振り返りをMPの中でも取り入れ、CXとしてOJTが完了した理想状態を改めて言語化、11期へ伝えていく。
また、11期が必要なときに必要な10期の軌跡にアクセスできるような場を整えていく必要がある。これは谷さんの力も借りながら作り上げていく。
■【周囲への感謝】リーダーやコーチに具体的に感謝したいこと■
誰から、どのような価値を頂きましたか。(感謝の気持ちも一緒に)
※最も潜在ニーズにアプローチし、必要であれば耳の痛いこともアドバイスしてくれたメンバーには名前の前に◎をつけてください。(1人のみ)
〇谷さん
同じMPのメンバーとして、何をどのように11期に引き継いでいくべきかを共に言語化することができました。
特に、11期に引き継ぐにあたっての、SLである自分に何を求めているのを伝えていただき、とても助かりました。ありがとうございます。
◎久野さん
CXのOJTを既に実施されている立場として、OJTを行う上での注意点を伺うことができました。
併せて、何を11期にきちんと伝え、何を思考してもらうかのきっかけも、久野さんへのコーチングを通して得られました。ありがとうございます。
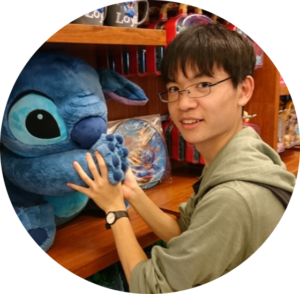
香山 渉
2023年01月10日
■研修を受けて■
・重要度と緊急度の2×2軸で優先度をつけた行動をするべきこと
・重要かつ緊急の事項を整理した後に無駄な行動をしがちであり、意識的に避けなければならないこと
・特に"運動"については後の祭りになる前に今のうちから定期的に実施をする必要があること
・表面的なwin-winではなく、相手のことを考えたwin-winを提案すること
・no-dealはお互いが約束を果たしているときにこそ起こり得ること
・自身が伝えたい時は、まず相手が伝えたいことを理解する必要があること
■今後に向けて■
【理想とのギャップ】
・「重要でない×緊急でない」事項につい時間を費やしてしまう場面があった
・「刃を研ぐ」にあたっての"精神"の部分に時間を充分に割くことができていないこと
【明日から意識すること】
・「重要である×緊急でない」事項に意識的に時間を割くことで、目の前の締め切りに追われる状態から抜け出していく。特に研究活動。そのために、研究自体の自身の目的を改めて言語化、残りの修士論文執筆までの1カ月間で週単位での進捗を可視化していく。
・"精神"の部分では、時間とお金が必要なことであった。いつでも実施することができるよう、自己啓発だけでなく小説を2冊に1冊の頻度で読む。
■研修講師(森口敦)へのメッセージ ■
本日も貴重な時間をいただきましてありがとうございました。
今年の抱負は「英語力の強化」「筋トレ継続」です。これら2つの目標を達成するため、本日の研修のように定期的に自身の活動を振り返り、第2領域にかける時間を意識的に増やしていきます。
この研修で「自分にも周囲にも誠実な人が自然とリーダーになり、組織を良くしていく」ということが身に染みて分かると思います。今までの自分のことは一切抜きに、今、そしてこれからのどれだけ自分に向き合い努力できるか。弱い自分を認め律していくことができる人にとっては、この研修はとても有意義なものになると考えています。皆さんのチャレンジと成長を心から応援しています。
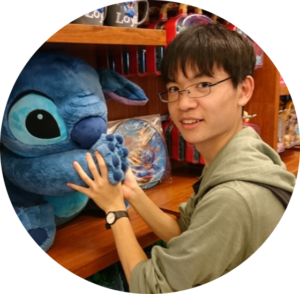
香山 渉
2023年01月07日
小松さんの記事から、当たり前のことを当たり前に実行することの重要性が伝わりました。メンバーや組織との信頼の面で、一度でも挨拶や時間厳守が守られない際には一気に信頼関係が無くなってしまうと思っています。小松さんは既に意識されていることから、エンター業務、運営面において、常に誠実なリーダーになってくれると強く感じました。応援しています!
責任を果たしていくために、権限を自らかき集めること。そして権限を集めるために義務を全うすること。それらを常に行いつつ、責任を引き受ける前には自分のキャパシティ含め責任・権限・義務を構造化し把握することを身をもって学んだ。
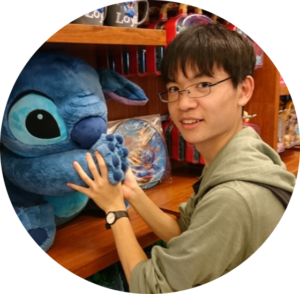
香山 渉
2023年01月07日
林さんの記事から、周囲への感謝を忘れないことが強く伝わりました。当たり前のことを当たり前にやってくれるメンバーに対して、つい感謝を疎かにしてしまうことがあります。林さんの研修で感じられた、周囲の人とその環境への感謝は、エンカレッジで活動する上で絶対に忘れずに持っていてほしいです。そうすれば作りたい組織や成果は自ずとついてきます。応援しています!
参加させていただく中で、自分の中にはトレード・オンの考えがかなり欠けていたことに気が付きました。目標達成を重視しすぎたり、あるいはモチベーションを重視しすぎたり、適度な塩梅でのコミュニケーションができていなかったことが、今までの失敗要因の最たるものであったように感じます。
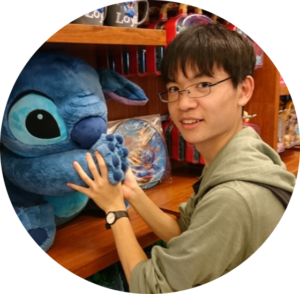
香山 渉
2023年01月07日
上原さんの記事から、私自身の学ぶ姿勢を見直すきっかけをいただきました。「振り返ってみると、研修中に...」の部分から、価値を受けるだけでなく、価値を提供していくこと、課題を自分事として前のめりに向き合っていくの重要性を感じられたのだと思います。応援しています!
会話でいかに自分が何も考えていないかを思い知り、自分と相手にとってwin-winな関係を築くための配慮を心がけようと思った。他者がどのように配慮しながらコミュニケーションを組み立てているかにも気付けるようになった。
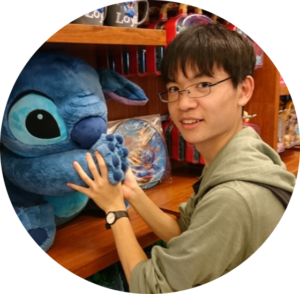
香山 渉
2023年01月07日
中条さんの記事から、責任権限義務の適切な設計の重要性を再認識しました。当たり前のことを当たり前にこなす人財に、責任権限義務が自然と集まっていき、責任を果たすことが楽しくなっていくと思っています。
これまで何度か研修でお見かけし、多くのことを吸収しようとする姿勢を見て自身も感化されてきました。引き続きよろしくお願いします!
社会人研修は、新卒で大企業に入社したらこのような感じなのか、と思いながら受けていました。すぐに使える技術や考え方が多く、実際に挨拶についてはすぐに改善できた。コーチングについては目から鱗で、理解しきれる部分は少なかったが、これから身につけていきたい技術だと思った。
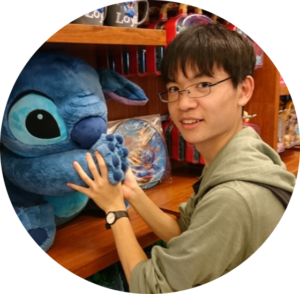
香山 渉
2023年01月07日
西川さんの記事を読み、「早く行動する」ことの重要性を再認識しました。"早く行動"するために、将来のことを予測して想定内のことを増やしておく必要があります。西川さんであれば、メンバーと強い信頼関係を築いたチームを作ることができると思っています!応援しています!
正直自分がいかにリーダーに足り得ないか、学ぶことができた研修であったと思う。そして、リーダーとして進むべき一歩とその先の方向性を示して頂いたものであるように思う。私はこの研修での経験・知識・憧れ・悔しさ・熱意を忘れずにリーダーたりうる人間に成長していきたい。
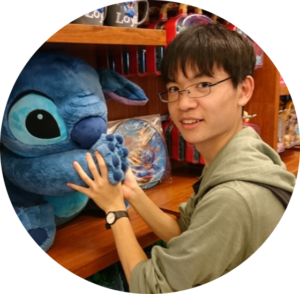
香山 渉
2023年01月07日
藤戸さんの記事から、知識だけでなく知恵を働かせることの必要性が強く伝わりました。エンカレッジの活動でも、前例のないことにどんどんチャレンジしていってほしいと思っています。
いずれ答えのない課題に直面するはずなので、その際には"鍛えた知恵"を思う存分発揮してください!応援しています!
初めてのリーダー経験において、偶然うまくいってしまったがために自身の実力を勘違いして慢心していたことに気づくことができました。研修を受け終えた今は、自分の真の弱みや甘さに向き合い、克服し、誠実なリーダーになりたいと心の底から思っています。
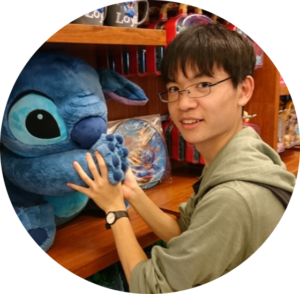
香山 渉
2023年01月07日
山口さんの記事から、信頼されるリーダーがどのような人であるのかを学んだことが強く感じられました。「当たり前のことを当たり前にやる」ことが自信を獲得、組織からの信頼を得、そしては成果に結びつくこと、エンカレッジの活動でこれから実感していくと思います。
私自身も"誠実"さについて自問するきっかけとなりました。ありがとうございます。これからも応援しています!
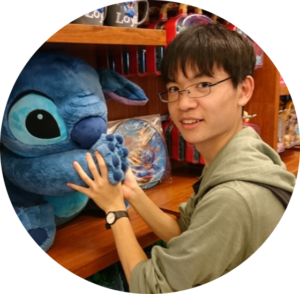
香山 渉
2023年01月07日
佐々木さんの記事から、組織の課題を自分事として捉え行動することの重要性を再認識しました。エンカレッジの活動では組織の課題を該当セクションだけではなく、他のセクションのリソースを使って解決するような場面も出てきます。その際には、本研修の学びを最大限に発揮して向き合っていただけたらと思います!応援しています!
知恵を使って行動することで最適な選択ができるということを学んだ。これからは、知識を知恵として活用していかなければいけない。知識はたくさんあるし、これからも増え続けるはずなのでここからは、それをどう生かすか考えていきたい。
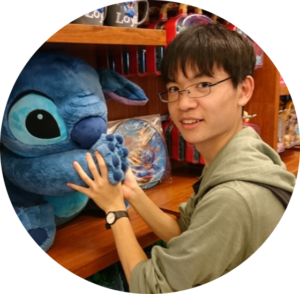
香山 渉
2023年01月07日
渋谷さんの記事を読み、昨年研修に参加したときの自分と重なるところを感じました。「自分が傷つかないように行動していた」の部分では、周囲との軋轢を生みたくないという思いから、非合理な決定に同調してしまう可能性があります。渋谷さんの経験から学ばせていただきました。ありがとうございます。
この研修を通じて、合理的な意思決定の重要性とその難しさに気づかれたのだと思います。応援しています!
リーダーシップゼミやビジネス基礎研修で学んだことを、机上の空論とせずに実践し続けることが重要。 プロジェクト年間計画をもとに毎月、リーダー同士でチームコーチングを実施します。 ※参加者同士で役割分担し運営する研修です。
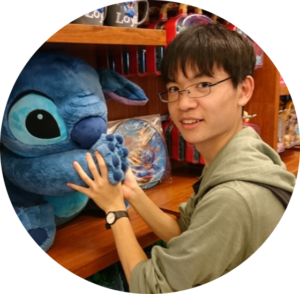
香山 渉
2022年12月16日
■【Goal】本日の目標と計画の宣言(SMART+C)■
1.先月・先週までの成果で、周囲の手本として伝えられること
・組織内の取り組みを組織外に発信してきたこと.
・セクション内でコラムの質を高めるにあたっての取り組み
・11期への引継ぎという観点で、何をどのようにどういった手段で残していくのかの考え方
・セクション内での情報共有にあたっての仕組づくり
2.来月の取組みで、周囲の手本として伝えられること
・エンターの中長期的なニーズをとらえた施策の実行
3.本日、誰に対し、どのような価値を具体的に提供したいか
・西本さん
→ 振り返り面談の履行進捗管理にあたって、セクション内で自身が整備してきたことを仕組み面からヒントを提供していきたい
・谷さん
→ コラム執筆にあたってのメンバーのモチベートについて、一執筆者として「どういったマネジメントが嬉しいか」の観点を提供したい
・池田さん
→ UAの獲得にあたっての意義をメンターに持ってもらうにあたって、一メンバーとして「どういった意義醸成の仕方や取り組みであればやりたいと思えるか」の観点を提供した。
■【Measure・Analyze・NextPlan】本日の振返り■
1.現状・成果の把握
(A)コラムの支部内外の立ち位置と、これまで提供してきた価値について再認識することができた。
(B)領域長の谷さんのコラム思いを改めて聴くことで、セクションにおける帰属意識(+モチベーション)に課題があると感じた。
(C)西本さんと池田さんからのコーチングの中で、自分が思っていたよりもコラムに対する認識に齟齬があると感じた。
2.ギャップの分析・課題の抽出
(A)コラムに対する認識の齟齬の観点で、セクションとしては記事を執筆している立場だからこそよく知っているが、メンターとしては記事の内容をそもそも知らないという観点に差があったのではないか。
(B,C)セクションのメんバーへの期待をこれまで伝えきれていなかったこと、特に引継ぎ業務についてメンバーに情報を公開できていなかったことが要因だと痛感。
3.今後の対策・計画
(A)改めてセクション内におけるコラムの立ち位置を再定義すると共に、メンター自身がコラムを活用したくなるような仕組み、コンテンツを作成、発信していく。
(B,C)引継ぎにあたって、どのようなことをどんな形で引き継ぐ必要があるのかをメンバーに直接伝えていく
■【周囲への感謝】リーダーやコーチに具体的に感謝したいこと■
誰から、どのような価値を頂きましたか。(感謝の気持ちも一緒に)
※最も潜在ニーズにアプローチし、必要であれば耳の痛いこともアドバイスしてくれたメンバーには名前の前に◎をつけてください。(1人のみ)
◎谷さん
本日はありがとうございました。SLと領域長の立場として、SLに求めていること、特に引継ぎにあたって自分がメンバーに対してするべきアクションが明確になりました。谷さんが「私は何をすればよいか」を自分に伺い、率直に伝えてくれたからこそだと思っています。これからも一緒に頑張っていきたいです。
・西本さん
本日はありがとうございました。コラムがそもそも支部内でそれほど浸透していない、という大きな気づきを与えてくれました。今回いただいたFBをセクション内に率直に伝えると共に、よりメンターに使ってもらえるようなコラムの発信の仕方を模索していきたいと思います。
・池田さん
本日はありがとうございました。メンターにコラムを活用してもらうにあたっての具体的な手段について気づきを与えてくれました。エンターとメンター双方がコラムを活用するにあたって、そのコラムが読みたくなるような特典について、セクションとして検討、実行していきたいと思います。
当たり前のことを実践し続ける。それこそがリーダーの近道。 主体性を発揮する。 目的をもって始める。 重要事項を優先する。 この当たり前のことを、『7つの習慣』をもとに深掘りしていきます。 評論家ではなく、我がこととして取り組むメンバーのための研修です。
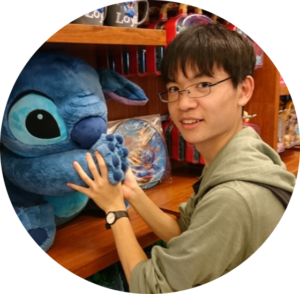
香山 渉
2022年12月10日
■研修を受けて■
【学び】
・パラダイムシフトを生み出すために,表面的なことではなく本質を見極める必要があること
・強いチームを作るために,自分に対して責任を持つだけでなく,チームとしての責任を持つこと
・影響の輪を広げることは重要であるが,関心の輪に無関心であると周囲のメンバーにたいして大変な迷惑をかけてしまうこと
・主体性を発揮していくために,自分ができることを考えて最善をつくすこと
・目的を見失わずに行動し続けるために,定期的に自分自身の行動を見直す機会を設けること
【現状との乖離】
・現在動かしているプロジェクトや参加しているイベントに関して,自分はできている状態であるが,チームとして責任を持って取り組めていない,という状態である.
・影響の輪を広げることに没頭し,関心の輪を広げていくことが蔑ろになっていると感じる.「面白い」と思ったことには即行動したいと思えるが,その面白みをさらに掘り下げていくような行動ができていない.
■今後に向けて■
・まずは自分が,という思考と行動はある程度できていると感じるので,チームのメンバーとしてどうあるべきか,に意識を向け行動をしていきたい.具体的には,自分からメンバーへ発信していくことに加え,メンバーが何を思い行動をしてくれているのかを発信してもらう場を設けたい.
・また,関心の輪を広げていくにあたって,自分自身が「やりたい」と思って行動をし始めたことを改めて振り返り,過去の自分に落胆されないように,今の自分を生きていきたい.
■研修講師(森口敦)へのメッセージ ■
本日も貴重なお時間をいただきまして,誠にありがとうございます.
遅刻するかもしれないという状況で,予めその設計をしていただいていたことがとても嬉しかったです.
2022.01.07
田村稔行 早稲田大学 基幹理工学部 情報通信学科
早稲田大学 基幹理工学部
コンサルタント・コーチ・メンター、政治家・医師・経営者、そしてチームリーダー。A&PROが関わる相手の多くが、自らの存在や組織をブランド…
人間力・仕事力を高めるWEB chichiの、「地球上で最も必死に考えている人にアイデアの神様は降りてくる」<ジャングリア沖縄の仕掛け人・森岡毅…
復習回数を闇雲に増やしたり、ノートいっぱいに何度も書かせる記憶法は、社会に出てから通用しない。 多忙なリーダーは、重要事項を一発で覚える。 たとえそれができなくても、復習回数を最小限にし、効果的・効率的に記憶することが大切。
窪田:中室先生はご著書『科学的根拠(エビデンス)で子育て』の中で、エビデンスを重視した教育の必要性を説いていらっしゃいます。そもそも金融業界にい…
クレド7.好奇心旺盛、常に学ぶ。 我々の活動における身近な事柄に興味を持ち、深く学ぶ事を大切にしていきます。教え上手は当たり前、学び上手であれ。…
コンサルタント・コーチ・メンター、政治家・医師・経営者、そしてチームリーダー。A&PROが関わる相手の多くが無形サービスを中心に活躍して…
コンサルタント・コーチ・メンター、政治家・医師・経営者、そしてチームリーダー。A&PROが関わる相手の多くが無形サービスを中心に活躍して…
顧客に新しい価値を創造し続けるためには自らの脅威と向き合い、あえて自社の優位性を覆していくようなサービス・プロダクト開発が必要です。
知識として体系化されているプロジェクトマネジメント。 ただし、頭で理解していても習慣化できていないと、顧客やステークホルダーの期待値とは程遠い『自己満足なプロジェクト』となってしまう。
組織で仕事をする上で社員や従業員に必要なものとされている「当事者意識」。当事者意識とは、どのようなもので、どうすれば高めることができるのでしょう…
当たり前のことを実践し続ける。それこそがリーダーの近道。 相乗効果を発揮する。理解してから理解される。刃を研ぐ。 この当たり前のことを、『7つの…
■今月の研修■ 『責任・権限・義務』 権限・義務の整合性を保ってこそ、理想の上司 『責任・権限・義務』のそれぞれが一体何なのか、またそれらがどの…
当たり前のことを実践し続ける。それこそがリーダーの近道。 目的をもって始める。重要事項を優先する。WIN-WINを考える。 この当たり前のことを…
世界有数の戦略コンサルティングファーム、マッキンゼー。同ファーム パートナーの久家紀子さんがお薦めする本は、村上春樹さんのエッセーやプラトンの哲…
当たり前のことを実践し続ける。それこそがリーダーの近道。 主体性を発揮する。 目的をもって始める。 重要事項を優先する。 この当たり前のことを、『7つの習慣』をもとに深掘りしていきます。 評論家ではなく、我がこととして取り組むメンバーのための研修です。
最近世の中の急激な変化によって注目されている「パラダイムシフト」。自分次第で可能性を広げられる学生だからこそ起こすことができたパラダイムシフトについて紹介します。あなたも当たり前に囚われない「諦めの悪い人」になりませんか?
次のような思いを持ったことはありませんか? 1.そんなつもりじゃないのに、誤解される......2.他の人に依頼しづらい......3.本当は気…
先日、採用をテーマとした講演を行った際、聴講者からこんな質問をもらいました。 「転職を考えたときに『自分の強みをつくりなさい』と言われ、いろいろ…
「メラビアンの法則」や「真実の瞬間」と向合い、各メンバー自身がブランド形成の重要要素であることを自覚していきます。 「目配り」「気配り」「心配り」の各段階を理解し、「マナー」「サービス」「ホスピタリティ」「おもてなし」の違いについて研究。 「マニュアル」「サービス」を理解・実践するのは当然。 「ホスピタリティ」「おもてなし」を顧客・メンバーに提供したいリーダーのための研修です。
行き過ぎた完璧主義は仕事を停滞させるだけでなく、自分自身を苦しませてしまいます。本記事ではプロジェクトマネジメントを題材に、自分の良さをかき消さず、最大限発揮する仕事への取り組み方を考えます。完璧主義で悩んだことのある皆さんに是非ご覧になって欲しい記事です。
新規登録
アカウントをお持ちの場合はログインする
香山 渉