【25年度・研修】ブランドマネジメント(基礎1)
2025.07.10
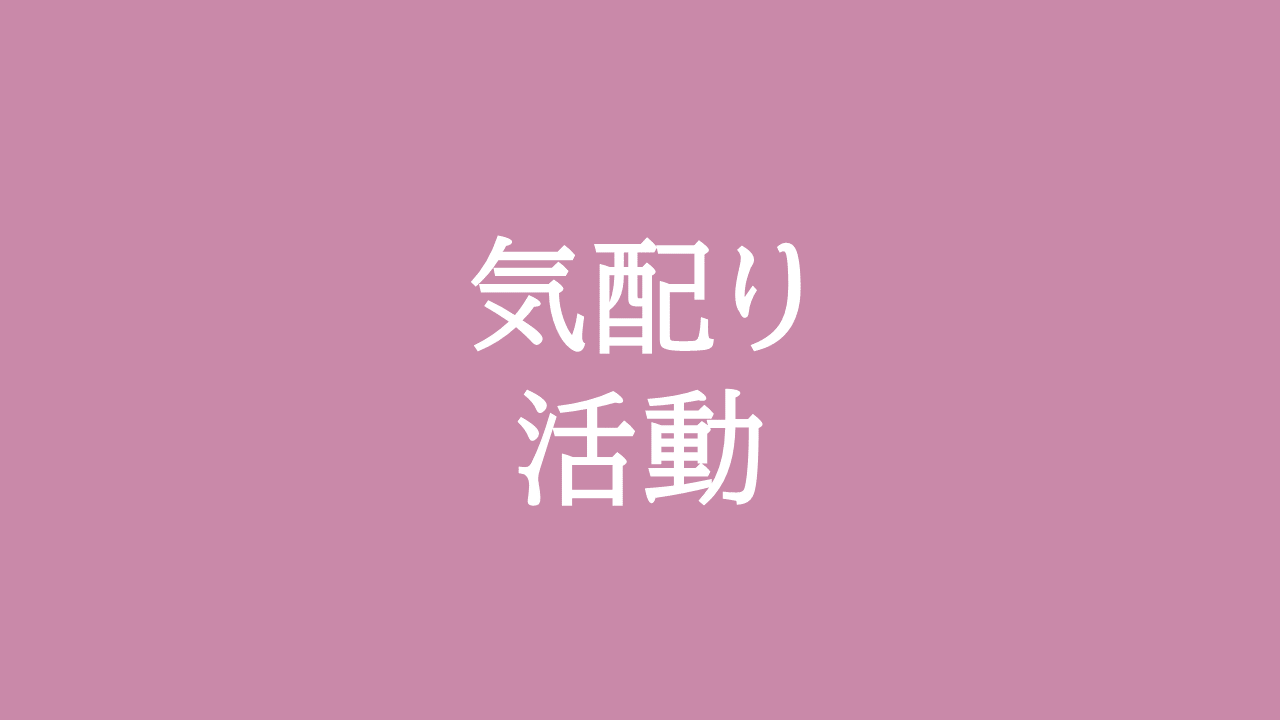
大きなプロジェクトを成し遂げる人は、日常の些細な業務も大切に取り組むことができる。一見目立たない、目の前の小さな仕事が、なぜ大切なのか?メンバーの体験記を通してご紹介します。
2025.07.10
2025.06.10
島元 和輝
2025.05.16
大庭彩
2025.05.10
木藤 大和
2025.04.10
島元 和輝
2025.04.03
大庭彩
コンサルタント・コーチ・メンター、政治家・医師・経営者、そしてチームリーダー。A&PROが関わる相手の多くが、自らの存在や組織をブランド…
人間力・仕事力を高めるWEB chichiの、「地球上で最も必死に考えている人にアイデアの神様は降りてくる」<ジャングリア沖縄の仕掛け人・森岡毅…
復習回数を闇雲に増やしたり、ノートいっぱいに何度も書かせる記憶法は、社会に出てから通用しない。 多忙なリーダーは、重要事項を一発で覚える。 たとえそれができなくても、復習回数を最小限にし、効果的・効率的に記憶することが大切。
窪田:中室先生はご著書『科学的根拠(エビデンス)で子育て』の中で、エビデンスを重視した教育の必要性を説いていらっしゃいます。そもそも金融業界にい…
クレド7.好奇心旺盛、常に学ぶ。 我々の活動における身近な事柄に興味を持ち、深く学ぶ事を大切にしていきます。教え上手は当たり前、学び上手であれ。…
コンサルタント・コーチ・メンター、政治家・医師・経営者、そしてチームリーダー。A&PROが関わる相手の多くが無形サービスを中心に活躍して…
コンサルタント・コーチ・メンター、政治家・医師・経営者、そしてチームリーダー。A&PROが関わる相手の多くが無形サービスを中心に活躍して…
顧客に新しい価値を創造し続けるためには自らの脅威と向き合い、あえて自社の優位性を覆していくようなサービス・プロダクト開発が必要です。
知識として体系化されているプロジェクトマネジメント。 ただし、頭で理解していても習慣化できていないと、顧客やステークホルダーの期待値とは程遠い『自己満足なプロジェクト』となってしまう。
組織で仕事をする上で社員や従業員に必要なものとされている「当事者意識」。当事者意識とは、どのようなもので、どうすれば高めることができるのでしょう…
当たり前のことを実践し続ける。それこそがリーダーの近道。 相乗効果を発揮する。理解してから理解される。刃を研ぐ。 この当たり前のことを、『7つの…
■今月の研修■ 『責任・権限・義務』 権限・義務の整合性を保ってこそ、理想の上司 『責任・権限・義務』のそれぞれが一体何なのか、またそれらがどの…
当たり前のことを実践し続ける。それこそがリーダーの近道。 目的をもって始める。重要事項を優先する。WIN-WINを考える。 この当たり前のことを…
世界有数の戦略コンサルティングファーム、マッキンゼー。同ファーム パートナーの久家紀子さんがお薦めする本は、村上春樹さんのエッセーやプラトンの哲…
当たり前のことを実践し続ける。それこそがリーダーの近道。 主体性を発揮する。 目的をもって始める。 重要事項を優先する。 この当たり前のことを、『7つの習慣』をもとに深掘りしていきます。 評論家ではなく、我がこととして取り組むメンバーのための研修です。
最近世の中の急激な変化によって注目されている「パラダイムシフト」。自分次第で可能性を広げられる学生だからこそ起こすことができたパラダイムシフトについて紹介します。あなたも当たり前に囚われない「諦めの悪い人」になりませんか?
次のような思いを持ったことはありませんか? 1.そんなつもりじゃないのに、誤解される......2.他の人に依頼しづらい......3.本当は気…
先日、採用をテーマとした講演を行った際、聴講者からこんな質問をもらいました。 「転職を考えたときに『自分の強みをつくりなさい』と言われ、いろいろ…
「メラビアンの法則」や「真実の瞬間」と向合い、各メンバー自身がブランド形成の重要要素であることを自覚していきます。 「目配り」「気配り」「心配り」の各段階を理解し、「マナー」「サービス」「ホスピタリティ」「おもてなし」の違いについて研究。 「マニュアル」「サービス」を理解・実践するのは当然。 「ホスピタリティ」「おもてなし」を顧客・メンバーに提供したいリーダーのための研修です。
行き過ぎた完璧主義は仕事を停滞させるだけでなく、自分自身を苦しませてしまいます。本記事ではプロジェクトマネジメントを題材に、自分の良さをかき消さず、最大限発揮する仕事への取り組み方を考えます。完璧主義で悩んだことのある皆さんに是非ご覧になって欲しい記事です。
新規登録
アカウントをお持ちの場合はログインする
木藤 大和