ここぞという場面で力を出せる人へ!
2022.07.04
クレド6. 大変なことこそ率先して楽しむ。守るな、攻めろ!
サービス深化・成長に近道なし。大変なことこそ深化・成長のチャンス。悩みながらも楽しむことで人生が豊かになります。
はじめに
多くの人が、受験や面接、試合などの大事な場面こそ緊張してしまうのではないでしょうか?適度な緊張は良い結果につながりますが、極度に緊張してしまうと、力を発揮できません。
そこで、今回の記事では「ここぞという場面で緊張してしまう人」に対して、緊張への対処法とそれを学んだ私自身の経験を紹介します。
緊張に対処する方法
緊張に対処するために、以下の2つが重要です。
- 入念な準備
- 「攻め」の行動
入念な準備によって、緊張を防ぐことができます。なぜなら、準備をすることで最善を尽くすことができ、自信につながるからです。誰しも、自信を持っていることに関しては緊張しません。緊張してから対処するのではなく、緊張しないように準備を徹底するのです。
しかし、十分に準備をしたつもりでも、緊張してしまうこともあるのではないでしょうか?緊張してしまった時には、「攻め」の行動をとることが有効です。緊張してしまった時の行動を、「攻める」と「守る」の2つに分けて考えてみます。
この場合の「攻める」とは、力を最大限発揮するために積極的に行動することです。一方、「守る」とはミスを最小限に抑えようとして消極的な行動をしてしまうことです。「守る」意識は失敗への恐れにつながり、さらなる緊張を生んでしまいます。
緊張に関する野球部での経験
ここでは、私が高校の野球部で経験した、緊張にまつわる出来事を紹介します。
緊張に負けた春の大会

私は2年生の春の大会で、ショートとして試合に出ていました。私は主にセカンドを守っていましたが、チーム事情によるポジション変更を受けて、ショートを守るようになったのです。
しかし、本来のポジションでないことに加えて日頃の取り組みも甘く、試合当日に異常に緊張してしまいました。足に力が入らず、終始フワフワした感覚でいたことを覚えています。さらに、先輩の代の大会でミスは許されないという意識がさらに緊張を強めました。
試合中は打球が近づくのを待つだけになって足が止まってしまい、体が強張ってミスを連発してしまいました。つまり、消極的な「守り」の行動をとった結果、力を発揮することができなかったのです。結果として途中で交代させられてしまい、チームも負けてしまいました。
今思えば、「入念な準備」と「『攻め』の行動」の両方が欠けており、当然の結果だったと思います。
緊張に打ち勝った夏の大会

春の大会での経験から、私は練習での取り組みを改めました。毎朝自主練に取り組むだけでなく、全体練習でも目的意識を持って取り組むようになったのです。努力の甲斐もあり、夏の大会でもショートとして試合に出ることになりました。
春の大会での失敗を繰り返さないために、私は夏の大会前日から当日にかけて入念な準備を行いました。例えば、前日寝る前に試合までの流れをイメージしました。また、当日の移動中には好きな音楽を聞いて周囲の音を遮断し、集中力を高めました。さらに笑顔と周囲への声かけを心がけ、打球が近づくのを待たず積極的に前に出る守備をすると決めて試合に臨みました。
結果として緊張することなくプレーすることができ、チームも勝利を収めました。「入念な準備」と「『攻め』の行動」の両方を十分にした結果、緊張に打ち勝つことができたのです。
おわりに
改めて振り返ると、緊張は起こるべくして起こることだと感じました。今後もプレッシャーのかかる場面が来ると思います。今回の記事が、読者の方々の緊張を和らげる助けになれば幸いです。

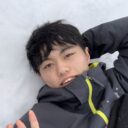













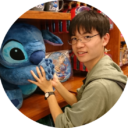








ログインするとコメントすることができます。
新着コメント