長年教育業界に勤めている方にこそ、受けてほしい。
2019.03.08
誠実かつ一生懸命であることの価値
今日の研修を通じて、誠実かつ勤勉であることの大切さに改めて気づかせていただきました。そして何事にも、誠実、一生懸命に取り組む姿勢を、しっかりと評価してくれる人がいる、職場があるということは、自分自身が忘れてしまっていた大切なことであると感じます。現在働いている他塾(利益追求型)でも、誠実さ、一生懸命さを忘れずに努力していこうと思います。
研修講師へのメッセージ
生き生きとお話をされている姿がとても印象的でした。今回の研修では、自分自身が今まで長年教育業界に携わっていたにも関わらず、仕事に対する向き合い方、取り組み方にまだまだ改善の余地があることを感じることができました。そうしたことを踏まえ、今後やるべきことを整理したうえで、具体的に行動に変えていこうと思います。
これから研修を受ける方々へ
この研修では、教育業界でどういった目的意識をもって働くべきなのかについて知ることができます。そして、研修参加者一人一人の仕事に対する向上心がアップすることも間違いありません。現在教育業界で働いている方々、特にただ漠然と仕事をしてしまっている方には、ぜひ一度この研修を受けてみることをお勧めします。最後になりますが、ぜひこの研修をより有意義なものとするために、誠意をもって参加し、学んだことを自分自身の中にしっかりと落とし込んでください。その上で、ご自身の経験の中で何か改善できることはないか、振り返っていただきたいと思います。
A&PROより
私たちも大事にしている誠実さや勤勉さ、一生懸命さに関する大切な気づきを得ていただきました。現在働いていらっしゃる他塾でも絶対に役立つことと思います。今後とも、誠実かつ一生懸命に、お互いの仕事に取り組んでいきましょう。(人財開発担当:萩原)
研修で学べたこと、感じたこと
[教室見学]
パーテーションのない開放的な空間で、笑顔で講師の方々が授業されている教室は、今まで見たことがありませんでした。
講師の方々、生徒さんの両方の能動的な姿勢が伝わってきました。
[ 教室見学以外]
本音で話せる関係が築けるという印象で、生徒はもちろん、働いている人を大事にする企業だと感じました。またこうした企業、人間関係の中で働くことで、自分もさらに成長できると感じました。



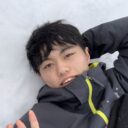











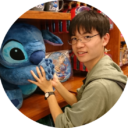








藤原穫