顧客ではなく、まずはメンバーを組織のファンにする
2023.03.28
10.顧客に感動を~高水準のサービスを追求し続ける~
感謝だけではなく、感動を与えてこそ、顧客に真の満足が生まれます。顕在ニーズに迎合せず、常に潜在ニーズにアプローチし続けます。顧客にファンになってもらう為に、まずは自分たちが組織のファンになるよう責任ある行動をしていきます。(責任・権限・義務の活用、頂いた金額の3倍の価値を提供する)
はじめに
皆さんは自分の所属する組織のファンになれていますか?
自分の所属する組織のファンになるってどういうことだ?と思う方も多いかと思います。顧客に組織のファンになってもらうために工夫することはよくあることだと思いますが、メンバーが組織のファンになるために工夫するという話はあまり聞かないのではないでしょうか。
この記事では、組織のファンになるとはどういうことか、またファンになることのメリットを紹介します。
組織のファンになるとはどういうことか
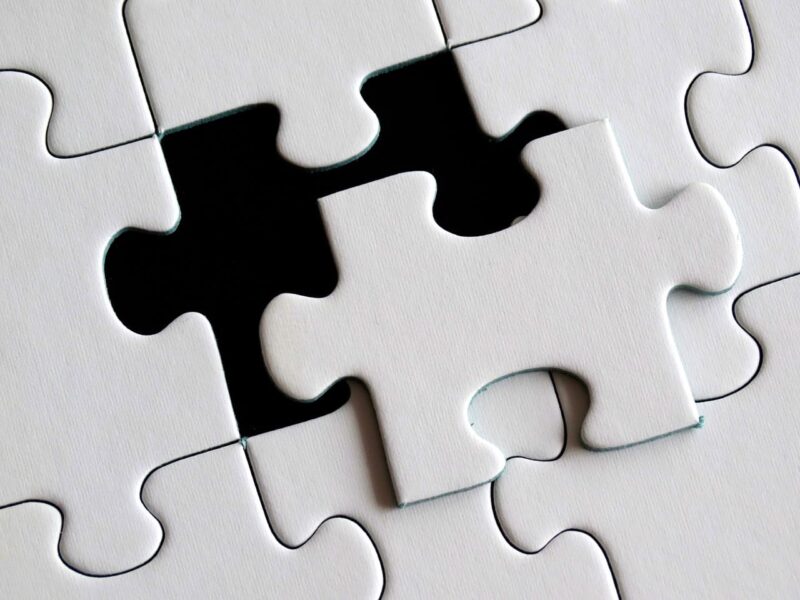
組織のファンになることは、自分の所属する組織に興味を持ち、組織の発展のために貢献する人になることだと考えています。端的に表現すると、組織の理念を理解し実践することです。
理念とは、組織の目的を示したものであり、組織が意思決定をする際に最も重要視されます。
例えば、A&PROでは以下の内容が理念となっています。
- 顧客・メンバーごとに、適切な指導効果がある教育機関であること (手法)
目的・目標を確実に達成するためのマインド・スタンス・スキルを個別設計で教育 - 顧客・メンバーの期待を、目標達成と人間的成長によって実現する教育機関であること (領域)
成果はもちろん、人間性も重視(目先の損得よりも、誠実に約束を守ることを重視) - 顧客・メンバーに尊敬され感謝される教育機関であること (深さ)
愛情・合理性を持って限界に挑戦できる厳しさのある文化を優先
理念とは組織がそうであろうとしている姿であり、その姿を実現し続けることが組織の本来あるべき姿でしょう。そのため、組織の理念を理解し、それを実践しようとすることは組織が本来あるべき姿であることに貢献することであり、組織の発展に貢献することになります。
そのため、理念の意味を理解し、日々実践しようとすることで組織のファンになるのです。組織全体のことを考えると、リーダーや特定のメンバーだけでなく、全てのメンバーが組織のファンになることが必要だと考えます。
メンバーが組織のファンになるメリット

ここまで組織のファンになることの意味を述べてきましたが、なぜメンバーは組織のファンになるべきなのでしょうか?
それは、顧客にも組織のファンになってもらうためです。
顧客はメンバーを見て組織を判断します。組織の目指す姿で対応するメンバーと、組織の目指す姿を理解せず独自の理念に基づいて対応するメンバーが混在していたとします。このとき、対応したメンバーにより、顧客の持つ組織に対する印象が大きく変わるでしょう。そのため、顧客の持つ組織の印象も顧客により変化してしまい組織のブランディングが困難になってしまいます。顧客の持つ組織のイメージが1つに定まらなければ、組織のブランドも確立できずファンを増やすことが難しくなるのです。
そのため、まずはメンバーが組織のファンになることが、顧客を増やすことに繋がり組織にとっては大きなメリットとなるのです。
組織のファンになる
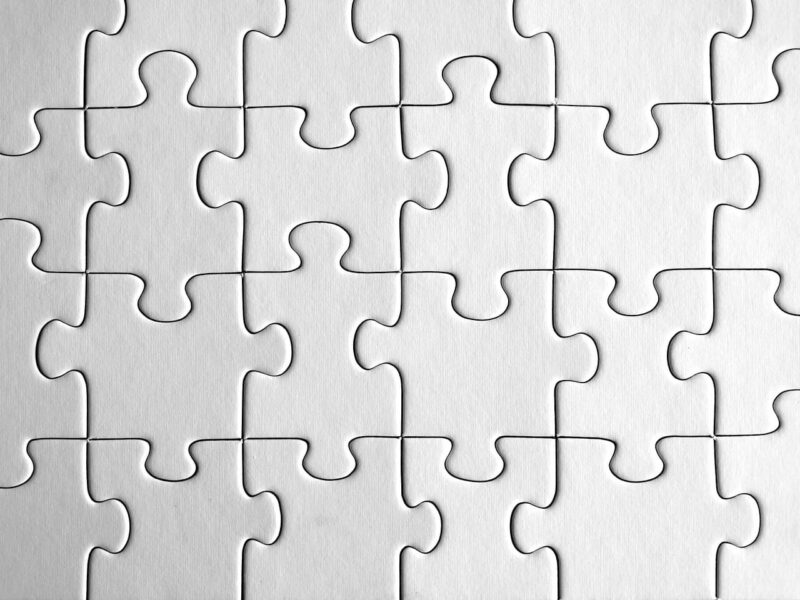
A&PROでは理念とクレドの両方が存在します。クレドは理念をより具体化しメンバーが理念を実践しやすくしたものだと考えています。私もA&PROにおいて、組織のファンになるため、理念・クレドを実践してきました。この記事もその活動の一環です。過去の経験を基にクレドを深掘りします。この記事執筆を通して、クレドの内容を正しく把握し、クレドを実践しやすくすることができたのです。
また、毎週のセルフブランディング研修でクレドの唱和を行うのですが、これは1週間に経験したクレドに関する話を他のメンバーに共有します。この活動を通して、他の人がクレドをどのように捉えているのか、実際にクレドの実践ができているのかを確認することができます。挙手制で発表を行うのですが、私は毎週必ず発表するようにしています。理念の理解が深まるだけでなく、人前での発表の練習にもなり、他者に気づきを提供できる機会でもあるからです。
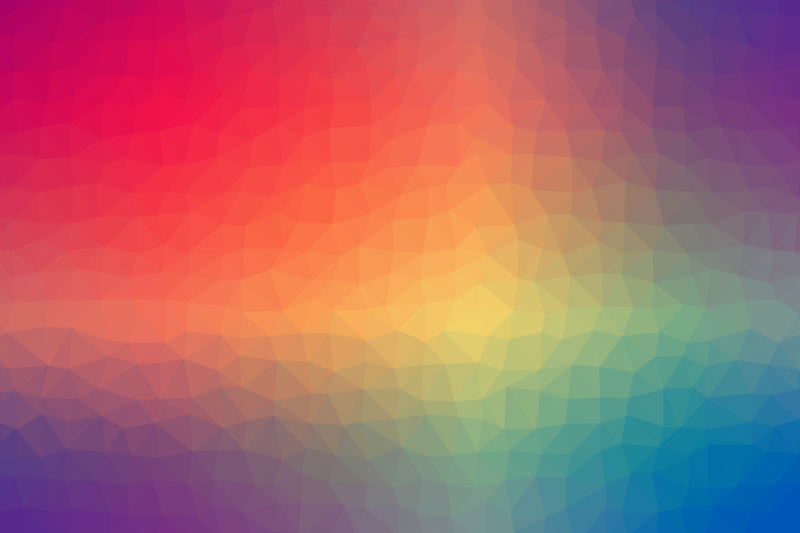
A&PROではこのような活動を通してメンバーがクレドを理解し実践できるような仕組みが作られています。私もその仕組みを活用しながら成長し、今では組織のファンになれたと思っています。
A&PROの研修に参加される方や、学習塾部門の生徒と接する際は理念を実践するよう細心の注意を払っています。上で述べたような活動があるからこそ、いざというときに理念に従った行動が取れるようになるのだと思います。
今後新しい組織に所属することもあると思いますが、どこの組織に行っても理念を確認し自分の取るべき行動を考えて活動します。また、自分以外のメンバーも理念を実践できるような仕組み作りにも目を向けていきます。このような活動を意識することで、組織の発展に貢献できる人財を目指します。







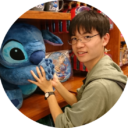















ログインするとコメントすることができます。
新着コメント