目配り・気配り・心配りは、気持ちだけでは不可能
2019.06.01
クレド3. 目配り・気配り・心配り、常に相手の立場に立つ
企業理念を判断基準とし、目配り・気配り・心配りの質を高めていきます。些細なことにこそ敏感に気づき、周りに共有することで、スピード対応に繋げます。生徒・保護者・メンバーの立場に立ち、一歩先行くサービスを提供していきます。
組織の一員として、相手を思いやる
今回取り上げるクレドを読んで、皆さんはどう感じるでしょうか?自分は当初、「1人の人間として、周りのことを考えることは当然だ」ぐらいにしか捉えていませんでした。しかし、組織の中で働くという経験を通して次のように考えを深めることができました。それは、目配り・気配り・心配りができる人間が、組織に貢献できる人財であるという事です。
こう考えるようになった明確なタイミングは定かではありませんが、今になって思い返すと、とても印象的な言葉があります。それが、上司である川瀬先生からの「仕事に余裕をもって取り組めるようになってほしい」という言葉です。もちろん大前提として、余裕をもって業務にあたることができればそれに越したことはありません。しかしこの言葉の真意は、次のようなことではないかと考えています。
自分の仕事に余裕を持てているからこそ、周囲を気に掛けることができ、必要な時に上司のサポートをしたり、後輩を育成したりすることができる。こうした意識のもとで日々の業務にあたることで、組織全体の動きを把握することができ、チームにとってなくてはならない存在になれるのではないかと感じました。実際川瀬先生が、ちょっとした異常にいち早く気づいて、ミスの重大化・顧客への被害を防ぐ場面、組織全体の運営に関わる仕事をされている場面が多々あります。こうした人財になれるよう、自分自身も日々レベルアップしていきたいと考えます。
生徒指導、そして社会人としてどう生かしていくか
上でも書かせていただいたように、自分の仕事に余裕を持って周囲に気を配るという事は直近の自分のテーマです。まず具体的に、日々の業務のなかで、直接的に関わっていないことに関して、何かしら気づきを探すという事を実践しています。こうすることで、部下としては、必要な時に上司のサポートができます。また上司としても、部下が犯す恐れのあるミスを未然に防ぎつつ、適度に黙って見守ることで後輩を育成することができます。この習慣は、常に忘れずに実践していきます。
そしてもう1つ、将来どんな環境で働くとしても取り入れたい直営塾ヘウレーカのシステムがあります。それが、業務関連のメールをメンバー間ですべて共有するというものです。部下の立場から考えれば、上司が日々どんな仕事をしているかを把握できます。これにより、 上司に時間を割いていただくことなく、 自分の仕事以外の知識やノウハウを速い段階から吸収できます。逆に上司からすれば、部下の仕事ぶりがリアルタイムで把握でき、その後の育成に活用できるほか、リスクマネジメントもしやすくなります。こうしたことを踏まえ、将来は上司・部下という両方の立場で組織に貢献できる、そんな人財として活躍します。



















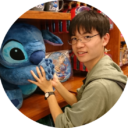







上野美叡