実はありがた迷惑!?メンバーに優しいけど組織に優しくない人の特徴
2022.12.15
今月の研修:理念のマネジメント
リーダーではないけど、メンバーの心のよりどころになり、求心力の高い人を一度は見たことがあると思います。このような人は、意外にも組織マネジメントをする上で邪魔になっている可能性があります。メンバーからの信頼を得たいと考えている人が陥りがちなミスです。あなたはそのような状態に陥った経験はありませんか?
優しい人がなぜ迷惑になるのか

結論から言うと、このような人は「情報の流れを悪くしている」ために組織の邪魔になっています。
本来プロジェクト内で何か問題があればメンバーは担当の上司かプロジェクトリーダーに直接相談する必要があるでしょう。なぜなら、リーダーが正しい判断を下すためにはその情報が必要だからです。メンバーから得られた多数の情報を判断材料として、リーダーはプロジェクトをより良い方向へ導いて行きます。
果たして、求心力を欲してメンバーの意見に耳を傾ける人が、本当に問題の解決に務めるでしょうか。単に相手に同情し、その場で愚痴を言って終わりになる可能性が高いでしょう。そもそもの情報が、リーダーまで共有されなければ解決しようがありません。そのような情報を集める人が途中にいると、本当に情報を知るべき人へ情報が届かず、問題解決に繋がらないのです。
サークル運営における私の経験

過去私も周りから頼られるためにそのような行動をしてしまったことがあります。
私はバドミントンサークルに所属しているのですが、このサークルでは7つほど係を作ることで運営を行っています。中には、責任も重大で、かつ重労働なシャトル係が存在しました。私は他の係の係長を務めていたのですが、そこの係長とは仲が良く、たまに愚痴を聞くことがありました。
シャトル係は毎回の練習に部室から使用する体育館にシャトルを届ける役割を持ち、彼らが練習に来ないと練習が始められませんでした。体育館は部室からも大学からも遠く、電車で30分ほどかかる距離にありました。また、シャトルは量も多くかさばるため、辛い肉体労働でもありました。
この係が辛いということはサークルの幹事長も理解していたでしょう。しかし、シャトル係の係長があまり主張しないタイプであったことも重なり、幹事長も正確な実態は把握できず、長いことこの問題は無視されてきました。
本来であれば、私がシャトル係の係長から係の仕事が大変だという話を受けた際に、幹事長に相談しよう、直接伝えようと言うべきでした。しかし、私はそのような提案はしませんでした。私とシャトル係の係長で解決策を考えはしたのですが、幹事長へ真面目な相談はされることなく、問題は未解決なままだったのです。

そんな状況が続き、結局問題は起きてしまいます。練習開始時間になってもシャトル係が現れず、シャトルが1つも無いために練習を開始できなかったのです。サークル員達は長いこと待たされることになりました。
原因は、シャトル係の人が授業後に体育館に向かう予定だったのですが、授業延長などにより、練習開始時間までにシャトルを持ってくることができなかったことでした。それを受けて、幹部と全ての係長が所属するグループで話し合いが行われました。
今まで、シャトルはその練習に参加するシャトル係1人に全て任されており、シャトル係の責任が重くなっていました。「練習に必ず参加する幹部にも少量のシャトルを持ってきてもらうことで、シャトル係が遅れても練習開始時刻は遅れないようにする」など、私も愚痴を私のところで止めてしまった罪悪感もあり、意見を積極的に述べました。
結果、その意見も採用されシャトル係の負担は軽減されることになりました。現在も、使用している体育館の近くにシャトルをおいておけるレンタルスペースを探すなど、シャトル係の負担を減らすために模索中です。
シャトル係の係長から仕事が大変だと話を受けた際に、幹事長に直接相談しようと私が提案できていればこのような問題は発生しなかったかもしれません。場合によっては私も一緒に相談しに行くなど、相談しやすい環境を作ることができたかもしれません。私の役目は愚痴を聞くことではなく、適切な場所に情報が届くようサポートすることでした。私が愚痴を聞いたことで、幹事長まで情報が届くチャンスが無くなっていたのかもしれません。
まとめ

人から信頼され、頼られるのは嬉しいことであり、自分の肯定感を高めることになるでしょう。承認欲求が強い人が、求心力を高めるための行動に出てしまうのだと思います。私も過去にそのような行動をしてしまったことがありました。しかし、本当に組織のことを考えるなら、この情報を本当に欲しがっているのは誰なのか、誰にこの情報を伝えたときが最も解決に近づくのかを考えるべきです。多くの場合は、決定権を持つ人に相談するのが良いでしょう。
皆さんも他者から情報を共有された場合は、その情報を得る人は自分で良いのか考えてみてください。私も、今後はただ情報を聞き、求心力を高めるような人ではなく、問題を解決に導くために行動していこうと思います。
これから研修を受ける方々へ
リーダーシップを発揮する人が何に気をつければ成長し続ける組織を作れるのか、その答えの一つが理念のマネジメントだと思います。プロジェクトのマネジメントを任されているが思うように進められない、これからプロジェクトをマネジメントする可能性があり今から準備しておきたいと考えている方におすすめの研修です。
研修で学んだこと
- 理念のマネジメント
- 権威のマネジメント








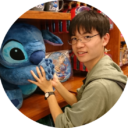

















ログインするとコメントすることができます。
新着コメント