真の指導者かどうかは、「心配り」で決まる。
2018.09.26
クレド3.「目配り・気配り・心配り、常に相手の立場に立つ」
企業理念を判断基準とし、目配り・気配り・心配りの質を高めていきます。些細なことにこそ敏感に気づき、周りに共有することで、スピード対応に繋げます。生徒・保護者・メンバーの立場に立ち、一歩先行くサービスを提供していきます。
クレドにまつわる私のエピソード
重要なのは「1人1人の立場になって考え、些細なことにこそ敏感に気づく」ことです。
生徒のために授業を行う、聞かれた質問に答える。これらは「サービス」であり、講師であれば必ず行うことです。しかし、単なるサービスを超え、本当に生徒のためになる指導を行うには、生徒が真に望んでいること・不安に思っていることにまで踏み込めるように目配り・気配り・心配りをすることが必要です。
例えば、学習塾へウレーカで働く講師は授業の合間を縫って、テーマ学習(目的・目標を持って取り組む自習)を行っている生徒に気を配ることで、夏休み明けで学校の疲れを感じている様子に気づき、見過ごさずに声掛けを行っています。その目的は、疲れている時こそ集中して取り組ませることで、日程がハードな入試期間でも集中力が途切れないような体力をつけるためです。だからこそ、生徒の変化に敏感に気づくことが大切です。
このように、まずは相手への目配りをしっかり行うことで、相手が何を望んでいるのか、どのような気持ちなのかを察知していきましょう。些細なことにも敏感に気づけるような心配りが、本当の意味での生徒指導に繋がるに違いありません。
生徒指導、そして将来医師としてどう活かすべきか
へウレーカで勤務させていただく中で、目配り・気配り・心配りが行えている講師ほど、生徒の変化に敏感に気づき、チームに共有していると感じています。医師となった際も1人1人の患者の変化に敏感に気づき、積極的にチームに共有することで、1人でも多くの患者を笑顔にしていきたいと改めて考えました。









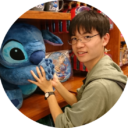













木藤 大和