one to oneマーケティングに欠かせないカスタマイゼーションの本質とは。
2021.04.27
今月のテーマ:サービス理論(基礎2)
生活にインターネットが浸透している現代、顧客は多様な情報を多様な方法で見聞きします。そうして世の中には多くのサービスが溢れていると知り、均質的ではない「私にぴったりのもの」があると考える顧客は少なくないのではないでしょうか。
そのような顧客を満足させるのが、one to oneマーケティング。これは顧客内シェア(特定の顧客に利用してもらう頻度・量)を伸ばすことを目標とするマーケティング手法です。本記事ではone to oneマーケティングの概念に基づき、顧客を満足させるために重要なことをご紹介します。
学習関係とカスタマイゼーション
顧客の欲求は多様ですから、それぞれの欲求に応じてサービスを適応させていく必要があります。しかし、顧客が変わるたびにサービスを一から作り上げていくのは非効率的で、大変な労力が必要となるでしょう。予めモジュール(平たく言えばパーツ)を複数用意しておき、それらを自在に組み合わせることでも、顧客の欲求に十分適うものを用意することができます。これをカスタマイゼーションと呼びます。
では、このモジュールの組み合わせはどのように設計すればよいのでしょうか。
企業は顧客の欲求を知る必要があります。ここで鍵となるのが学習関係。学習関係とは、顧客から設計のための判断材料を引き出す、つまり顧客について学ぶことができる状態のこと、さらには顧客が「企業に判断材料を渡すと良い」と学ぶことも指す言葉です。
企業に渡した判断材料のおかげでひとたび満足できるサービスを受けられたなら、顧客はより多く、頻繁に判断材料を渡すようになり、好循環が生まれるでしょう。これはまさにone to oneマーケティングの目標である顧客内シェアの拡大を意味します。

私は、カスタマイゼーションの本質は企業が顧客に対して責任を持って選択肢を提案することであると考えました。
モジュールやその組み合わせがあっても、最終的にそのサービスを受けるかどうかを選ぶのは顧客です。しかし、だからと言って顧客任せにしてはいけません。それではマスマーケティング(市場内シェアの増加を目指す手法)と変わりありません。
カスタマイゼーションでは、それぞれのモジュールやその組み合わせについて説得力ある根拠付けをする必要があります。メリットだけでなくデメリットも説明する、他の顧客による体験談を紹介するといったことです。
選択を顧客任せにしてしまえば、仮に顧客が満足したとしてもそれは自身の選択が正しかったと考えるのみで、企業と顧客の信頼関係は発展しないかもしれません。もう一度サービスを利用してくれる可能性もそう高くはないでしょう。
とある酒屋さんにて
具体例として酒屋さんの話を挙げます。私の家の近くの酒屋さんでは、日本酒の試飲をさせてくれます。
あるお酒を試飲して私が好ましい反応をしたとき、店員さんは「このお酒が好みなら淡麗な味わいがお口に合いますかね。こちらも試してみますか?」と他のお酒も提案してくれました。
購入したお酒が満足なものであったとき、店員さんの提案があった場合となかった場合の違いを想像してみてください。もし提案がなかったら、同じようなお酒を買うとしてもそのお店にこだわることはないでしょう。ショッピングサイトで注文して配送してもらう選択肢もあります。
しかし実際には提案がありました。私はこう考えたわけです。
「次に日本酒を買うときも、あの店に探しに行こう」と。
私の好みに合わせてお酒を提案してくれたこの酒屋さんは、まさに判断材料をもとにモジュールをカスタマイゼーションしてくれたといえるでしょう。そして顧客内シェアも広がったといえるわけです。

この本質をどう活かせるか
私はA&PROにおいて、本質にこだわった記事執筆を通して、メンバーをリーダーとして育成させるプロジェクトを行っています。私自身リーダーとして、メンバーに積極的に提案を行うことがありますが、今回の研修での気付きをその提案に活かすことができると考えました。それはつまり、提案するだけでなく、なぜその提案が妥当かを根拠を含めて説明することです。基本的ではありますが、相手の状況に合わせた提案・根拠づけが、メンバーからの信頼につながるかもしれません。
これから研修を受ける方々へ
本研修では、one to oneマーケティングを構成する5つの概念を具体例とともに深掘りしました。私は世の中の具体例、自身の活動における具体例について考えていく中で、「いま、ここ」のサービス、「私だけの」サービスが喜ばれるのだろうと気付きました。ぜひ、参加されるあなたも、研修資料には載っていない独自の気付きを見出してみてください。研修をより自分のものにできることでしょう。
研修で学んだこと
- マスマーケティングは市場内シェアの拡大が目標、one to oneマーケティングは顧客内シェアの拡大が目標。
- 企業側の重要度に応じて顧客を識別する。
- カスタマイゼーションは学習関係に基づく。
- 一過性の売り上げではなく、生涯価値を重視。

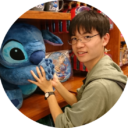
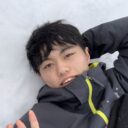























ログインするとコメントすることができます。
新着コメント