【25年度・研修】コーチング理論(基礎3)
2026.01.10
2026.01.10
2025.12.10
川瀬 響
2025.11.10
川瀬 響
2025.10.10
川瀬 響
2025.09.10
川瀬 響
2025.08.10
川瀬 響
2025.07.10
川瀬 響
2025.06.10
川瀬 響
2025.04.10
川瀬 響
2025.03.10
川瀬 響
2025.02.10
川瀬 響
2025.01.10
川瀬 響
2024.12.10
川瀬 響
2024.11.10
川瀬 響
2024.10.10
川瀬 響
2024.09.10
川瀬 響
2024.08.10
川瀬 響
2024.07.10
川瀬 響
2024.06.10
川瀬 響
2024.05.10
川瀬 響
2024.04.10
川瀬 響
2024.03.10
川瀬 響
2024.02.10
川瀬 響
2024.01.10
川瀬 響
2023.12.10
川瀬 響
2023.11.10
川瀬 響
2023.10.10
川瀬 響
2023.09.10
川瀬 響
2023.08.10
川瀬 響
2023.07.10
川瀬 響
2023.06.10
川瀬 響
2023.05.10
川瀬 響
2023.04.10
川瀬 響
2023.03.10
川瀬 響
2023.02.10
川瀬 響
2023.01.10
川瀬 響
2022.12.10
川瀬 響
2022.11.10
川瀬 響
2022.10.10
川瀬 響
2022.09.10
川瀬 響
2022.08.10
川瀬 響
2022.07.10
川瀬 響
2022.06.10
川瀬 響
2022.05.10
川瀬 響
2022.04.10
川瀬 響
2022.03.10
川瀬 響
2022.02.10
川瀬 響
2022.01.10
川瀬 響
2021.12.10
川瀬 響
2021.11.10
川瀬 響
2021.10.30
2021.10.10
川瀬 響
2021.09.10
川瀬 響
2021.08.10
川瀬 響
2021.07.10
川瀬 響
2021.06.10
川瀬 響
2021.05.10
川瀬 響
2021.04.10
川瀬 響
2021.03.10
川瀬 響
2021.02.10
川瀬 響
2021.01.10
川瀬 響
人が自ら動きたくなる組織には、「信頼」「理解」「成長支援」の3つの要素があります。 本研修では、マグレガーのXY理論・マズローの欲求5段階・コーチングの領域モデルを用いて、 「人はなぜ動くのか」「どうすれば自ら動くようになるのか」を、実例を交えて深く学びます。 単なる知識の習得にとどまらず、現場で直面する課題(メンバーの停滞・生徒の伸び悩み・顧客対応の難航など)を、“人間理解”を通して紐解く実践型のプログラムです。
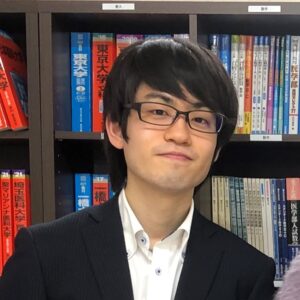
川瀬 響
2026年01月10日
■研修を受けて■
●コミュニケーションの取り方
・「もし○○だったらどう思うか?」
リソースや成功体験、「どんな意味があるのか?」といった手法がある。特に、目的・意味を見失っていないかどうかは常に気をつけたい。
●マズローの欲求5段階
・同じ人でも、領域ごとに欲求段階が異なる。
・下から順番に満たしていくことが重要。
●マグレガーのXY理論
・どちらか一方のみを使うのではなく、X理論とY理論を使い分けることが重要。
※自分が受けてきた手法で、相手にも対応しがちであるので、注意。
●コーチングの領域
・見えていることだけで対応してはいけない。
※ミスが多い場合は、家庭の事情・学校などでの事情・体調面や精神面など、さまざまな要因が隠れている可能性がある。
■今後に向けて■
・「相手は成長しようと思っている」「相手の存在を信じる」は、当然のことではある一方で、目の前のことに熱中するとつい忘れてしまいがちなポイント。
→ことあるごとに、原点に立ち返ることを大切にしたい。
→口で言うだけでなく、行動で示すこと。(応援していることを伝える。課題に対して提案できる準備をする。)
■研修講師(森口敦)へのメッセージ ■
初心に帰ることの重要性を改めて感じました。
本気で相手のことを考えるとはどういうことなのか、常に意識していきたいと思います。
本日もありがとうございました。
1/11 川瀬
人が自ら動きたくなる組織には、「信頼」「理解」「成長支援」の3つの要素があります。 本研修では、マグレガーのXY理論・マズローの欲求5段階・コーチングの領域モデルを用いて、 「人はなぜ動くのか」「どうすれば自ら動くようになるのか」を、実例を交えて深く学びます。 単なる知識の習得にとどまらず、現場で直面する課題(メンバーの停滞・生徒の伸び悩み・顧客対応の難航など)を、“人間理解”を通して紐解く実践型のプログラムです。
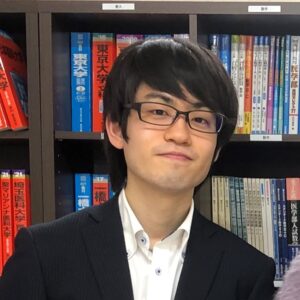
川瀬 響
2025年12月10日
■研修を受けて■
・コーチングのポイント
→相手は成長したいと思っている、相手が決断する、答えを見つけ出すパートナーになる
・関係の築き方
→相手の存在を信じる、相手の考えを受け入れる、相手の気持ちに共感する(×同情する)
・積極的傾聴
→集中して聞く、促しながら聞く、価値判断しない
■今後に向けて■
・(相手が成長したいと思っていることが前提で、)相手のポジティブポイントを見つけること
→一見、不平不満に聞こえることも、本人の中に「こうしたい!」というニーズがあるからこそ。
・苦しい過去(現実を見る)、苦しい未来(悪しき習慣を断つ)、楽しい過去(モチベーション)、楽しい未来(目的)を使い分けられるように。
■研修講師(森口敦)へのメッセージ ■
コーチングの実践は久々でしたが、改めてポイントを再確認できて、良い学びになりました。
特に、ポジティブポイントを見つけることを徹底したいと思います。
本日もありがとうございました。
12/10 川瀬
人が自ら動きたくなる組織には、「信頼」「理解」「成長支援」の3つの要素があります。 本研修では、マグレガーのXY理論・マズローの欲求5段階・コーチングの領域モデルを用いて、 「人はなぜ動くのか」「どうすれば自ら動くようになるのか」を、実例を交えて深く学びます。 単なる知識の習得にとどまらず、現場で直面する課題(メンバーの停滞・生徒の伸び悩み・顧客対応の難航など)を、“人間理解”を通して紐解く実践型のプログラムです。
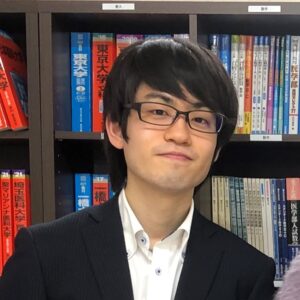
川瀬 響
2025年11月10日
■研修を受けて■
●コーチング
・目的・目標とモチベーションを結び付ける
★潜在ニーズにアプローチすること
・目標に向かって主体的に取り組むように導く
●コーチングとティーチング・カウンセリング
・コーチングは、生存欲求・安全欲求が満たされていない人には適切でないことがある。(本人に考えさせるよりも、まず指示を出した方が良い・まず話を聞いた方がよいことがある。)
●マズローの欲求5段階
・生存欲求→安全欲求→社会的欲求→承認の欲求→自己実現欲求
・下の段階の欲求が満たされないと、上の段階の欲求は満たされない
・コーチがクライアントの成長を信じることが、クライアントの成長に繋がる
●ノルマとコミットメント
・動機が自分の中にあるのか、外部から与えられているのか
→外部から与えられたものだとしても、自分の成長のために再定義することで、モチベーションを高めることができる
・あえて高めの目標を設定することも戦略として考えられる。(コーチがコントロールできる場合)
●コーチングの実践
・「現状がどうなのか」→「このままだとどうなってしまうのか」→「うまくいっていた時はどうだったか」→「今後どうするべきか」という流れ。(必ずしもそうでないといけないわけではない。各領域ごとの目的を踏まえて活用していくことが重要)
■今後に向けて■
・そもそも、目的・目標の重要性を伝えられるように準備すること
→潜在ニーズにアプローチすること
・生徒自身が、自分で解決策を見つけることを大切に
→必要に応じて提案はするが、自分で決めさせる
■研修講師(森口敦)へのメッセージ ■
各生徒たちが、勉強への向き合い方から見直せるように、準備していきたいと思いました。大学受験のためにはもちろん、その先の社会人として活躍するうえで、どう行動すべきなのか・どう行動すると素敵なのか、生徒自身が考えられるようにしていきたいと思います。
本日もありがとうございました。
11/10 川瀬
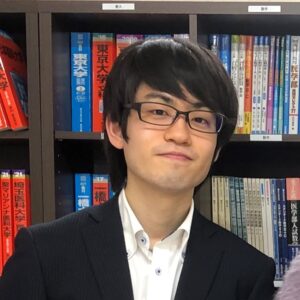
川瀬 響
2025年10月10日
■研修を受けて■
・ブランド:モノやサービスについて抱くイメージ、価値
※モノやサービスを購入する前に、『顧客』が持っている
・ブランドは、商品だけでなく、体験で作られる。
(AppleStore...製品と同じく、洗練されたイメージ)
・ブランド・エクイティ・ピラミッド
→マーケット、ターゲット、提供する価値、その根拠、価値提供の手段、人格
※提供する価値は目に見えないもの、手段は目に見えるものであることが多い。
■今後に向けて■
・ターゲットを意識すること
→まずは、どのような生徒・保護者に向けてサービスを提供するのか。アンマッチが生じないように。
※「伸び悩んでいるが成長したいと思っている生徒とその保護者」がコアなターゲットになると思う。
・常に目的を意識すること
→生徒・保護者に何を提供するのか。というよりも、それを提供した結果、生徒・保護者にどんな価値を感じてほしいのか、どうなってほしいのかが(ブランディングとしては)本質。
■研修講師およびチームリーダーへのメッセージ ■
本当の意味で価値を提供できる人材になるために、重要な内容を学べたと感じます。
ブレない強さと変化を恐れないしなやかさを身につけていきたいと思います。
本日もありがとうございました。
10/10 川瀬
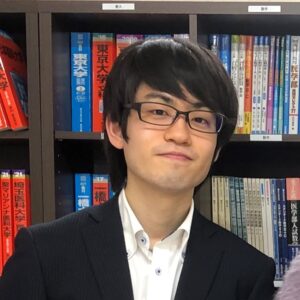
川瀬 響
2025年09月10日
■研修を受けて■
・災害時の緊急対応
→緊急度・頻度に応じて対応を準備していくことが重要
マニュアルを見て対応できるもの・できないものを区別して、準備する。
また、遭遇する可能性の高いものから準備していくことが重要。
■今後に向けて■
・いざという時に行動できるように準備しておくことが重要。
(実際の災害時は想定を超えることも起こりうるからこそ、当たり前のことで判断・決断のリソースを割かない。)
→必ずやるべきことは、迷わずに行動できるように普段から練習していく(生徒の安全確認・的確な指示だし・避難経路の確保など)。
→優先順位を明確にする(まず命の確保、避難経路の確保)
■研修講師(森口)およびリーダー(川瀬)へのメッセージ ■
実践の場があるということが、有難いと感じました。
いざという時が来ないことを祈りますが、いざという時に大切な命を守れるように準備したいと思います。
本日もありがとうございました。
9/10 川瀬
責任・権限・義務。 言葉だけを知っていても意味がない。 責任・権限・義務の違いと互いの関係 報告・連絡・相談の違いと「判断・決断」との関係 報告・連絡・相談のタイミングと「マネジメント・人材育成」の関係 これらを理解し、効果的に使い分けることが重要。 理屈と機能を理解し、チームワークを大きく向上したいリーダーのための研修です。
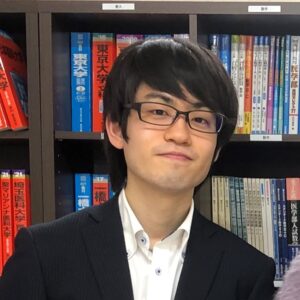
川瀬 響
2025年08月10日
■研修を受けて■
●責任とは
→対応できる状態でいること。想定外をできる限り小さくすること。
●責任・権限・義務
→責任を全うするための権限。権限に対応した義務。
→責任を全うするために、権限を自ら積極的に求める姿勢が重要。
→『権限をくれないからできない』『権限をくれ』というメンバーに対する対応。(権限を自分からもらいに行くこと。権限をもらえるように義務も含めて説得力のある提案をすること。)
●じんざい
→メンバー育成にも活用。なぜ権限を渡すのか/はく奪するのか、説得力を持って伝えられるようにすること。
●報告・連絡・相談
→リスクヘッジ可能なタイミングで行うこと
(相談すべきことが報告になってしまっては、上司もアドバイスができない。)
●クレド
→企業理念を体現するための行動基準
→メンバーが自主的に行動するための道しるべ
■今後に向けて■
●責任を全うすることを最優先に考える
→必要な権限を見つける力。第三のアイデアを見つける力。
●相手の時間をいただく以上、価値のある時間にすること
→説得力のある提案
→成長を実感できる授業
→意義を感じるガイダンス
■研修講師(森口敦)へのメッセージ ■
事前の準備の重要性を改めて感じました。
目的を意識すること、判断材料を集めることを特に大事にしていきたいと思います。
本日もありがとうございました。
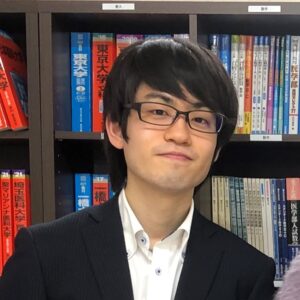
川瀬 響
2025年07月10日
■研修を受けて■
●ブランドマネジメント
→信頼と同じく、良いブランドを築くには日々の積み重ねが重要だが、悪いブランドを築くのは簡単。
→ブランドを築くことで、無形サービスの特徴である無形性を克服することにもつながる。
(顧客は、事前にサービスを確認できなくとも、「この企業ならきっと価値のあるサービスを提供してくれるはずだ」という信頼を獲得することができる。)
→「他社との違い」「WEBコンテンツとの違い」「AIとの違い」などを踏まえ、自分たちだからこそできることを常に考え、実行していくことがブランド形成の第一歩。
■今後に向けて■
・普段の指導から、ブランドを意識して行動すること
→気付いた時のみ実践するのではなく、日々・1秒1秒大切にしていくことで、ブランドの形成に繋げる
・危機をチャンスに変える
→クレーム対応は迅速に、重大にとらえる。
■研修講師およびチームリーダーへのメッセージ ■
日々の指導から、ブランドを築いていくという意識を大事にしたいと思います。そのためにも、初心に帰って、生徒を絶対に伸ばすという意識を持ちながら指導・準備・戦略会議を丁寧に行っていきたいと思います。
本日もありがとうございました。
7/10 川瀬
復習回数を闇雲に増やしたり、ノートいっぱいに何度も書かせる記憶法は、社会に出てから通用しない。 多忙なリーダーは、重要事項を一発で覚える。 たとえそれができなくても、復習回数を最小限にし、効果的・効率的に記憶することが大切。
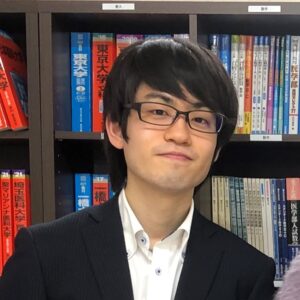
川瀬 響
2025年06月10日
■研修を受けて■
●記憶のメカニズム:
感覚記憶⇒短期記憶⇒長期記憶
・大脳に入った情報は、海馬で取捨選択され、必要と判断されたものが大脳皮質に移行し、長期記憶に移行する
・扁桃体を刺激することで、情報を必要と判断されやすくなる
⇒主体性・楽しさ・繰り返しが重要
●長期記憶の分類:
陳述記憶と非陳述記憶に分けられる
・陳述記憶:エピソード記憶・意味記憶
・非陳述記憶:手続き記憶・プライミング・古典的条件付け・非連合学習
⇒生徒指導においては、エピソード記憶・意味記憶・手続き記憶が重要
●シナプスの可塑性
・神経伝達物質が大量に放出されることで、シナプスの増強が起こる。(使われないシナプスは弱まる)
⇒繰り返しの刺激・強い刺激を与えられるか
●睡眠の重要性
・レム睡眠によって大脳のシナプスの整理が行われる。
⇒長期記憶の定着につながる
・レム睡眠は睡眠の後半に多いため、7時間程度の睡眠が重要になる
■今後に向けて■
・復習の手順まで伝えていくことの徹底
⇒どのタイミングで復習をするのかを伝える・実践できているかまで確認する(復習ノートの日付確認)
・知識も、自分で調べることを基本にする(参考書の活用)
・イメージしづらい知識に対して、具体例を説明したり覚え方を説明したりするところで、生徒に価値を提供していく
・チラシに対しても、記憶のメカニズムを活用できる
⇒感覚記憶をまず短期記憶にするために?
⇒チラシの色使いやフォントの大きさ・配布時の声掛けの仕方(相手の目を見る、挨拶をする、医学部を強調する!)
■研修講師(森口敦)へのメッセージ ■
本日もありがとうございました!
生徒自身が記憶のメカニズムを活用し大学以降の学びに生かせるように、目的・意図を伝え、学習法を定着させていきたいと思います。
6/10 川瀬
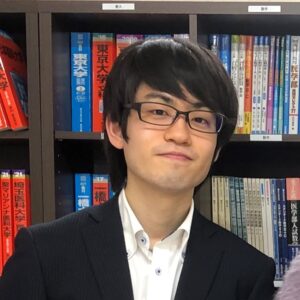
川瀬 響
2025年04月10日
■研修を受けて■
●無形サービスの特性
・無形性:サービスを事前に確認できない
★可視化することが重要。(Gmap-cシートなど)
・非分離性:生産と消費が同時
★消費者の様子を見ながら、生産物をカスタマイズできることが強み
・変動性:提供者・環境によるサービス品質の変動
★チームでの理念や大事にすべきことを共有することが重要
・即時性:在庫をもてない
★固定シフトを大事にすることが重要
●サービス品質の決定要因(一部)
・信頼性:サービス品質を信頼できる
★「できること」「できないこと」を明確にすることが重要
・反応性:顧客の求めに迅速に応じることができる
★顧客の求めに先回りして準備すること・顧客からの求めがあった際に、迅速に動くことが、顧客への安心感・信頼感につながる
・確信性:必要なサービスを提供できることを確信させられる
★必要なサービスを提供することが相手への「礼儀」
・共感性:相手の個人的状況・気持ちに共感できる
★相手の成長を本気で考えていることを伝えていく
■今後に向けて■
・塾は、教室という場そのものがサービスになりうる
⇒生徒たちが主体的に真剣に学びに向き合える場を作る。
・生徒、保護者対応を迅速に動く意識する。
⇒相手に言われる前に動く。踏み込むこともためらわない。
■研修講師およびチームリーダーへのメッセージ ■
塾全体を見渡す視点を持って、指導にあたりたいと改めて感じました。
本日もありがとうございました。
4/10 川瀬
知識として体系化されているプロジェクトマネジメント。 ただし、頭で理解していても習慣化できていないと、顧客やステークホルダーの期待値とは程遠い『自己満足なプロジェクト』となってしまう。
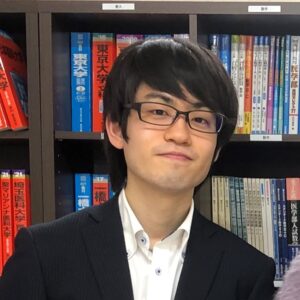
川瀬 響
2025年03月10日
■研修を受けて■
●プロジェクトとは
・独自性・有期性のあるもの ⇔ 定常業務
●プロジェクトの重要性
・環境の変化の多い時代(デジタル化・AIなど)
→変化に適応して生き残るために、普段から業務に対して目的・目標を設定・見直しをし、行動していく習慣が大事になる。
→実は定常業務も、プロジェクトとしてとらえることができる。
※たとえば清掃業務であれば:「より効率的に清掃するには?」→「清掃する順番の検討」「新しい清掃用具の検討」など
●プロジェクトの不確実性
・今まで通りのことを実行するわけではないからこそ、プロジェクトには不確実性がつきもの
→不確実性があるから実行しない、ではなく、不確実性を小さくしていく努力が重要
→適切なミーティング・面談での判断や決断
●プロジェクトの不確実性を減らすには
・不確実性を小さくする:計画を立てる、判断材料を集める
・バッファをもつ:余裕をもつ(時間的資源・金銭的資源など)
・実行しながら不確実性を小さくする:たたき台をつくる、実行しながら測定・改善する
■今後に向けて■
●測定を効果的にする
・目標に対して適切な指標を設ける
※顧客満足度の測定→アンケートの実施など
●新しいことへの挑戦
・今までにないことに挑戦することを大切に
※生徒募集、顧客内シェアも含む
■研修講師(森口敦)へのメッセージ ■
生徒・保護者に対してどういう価値を提供していくのか、
改めて見つめ直していきたいと思います。
また、積極的にプロジェクトを実行し、変化に適応できる柔軟性も身に着けていきたいと思います。
本日もありがとうございました。
3/10 川瀬
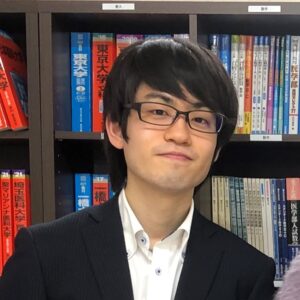
川瀬 響
2025年02月10日
■研修を受けて■
●「理解してから理解される」
・win-winの関係を築くために、まずはこちらが相手を理解すること
※医者が、診断してから薬を処方するのと同じ
・共感しながら話を聞くことが重要
準備がおろそかだと、「聞くふり」「選択的に聞く」で終わってしまう。
●「相乗効果を発揮する」
・チームメンバーの強みを発揮するために、
お互いの違いを尊重して、第3の案を生み出すこと
※お互いが主体性を発揮していることで、相乗効果は生まれる。
win-loseやlose-winの関係だと、妥協案に留まってしまう。
●「刃を研ぐ」
・プロジェクトや人生の目標を達成するうえで、
肉体・精神・知性・社会性を磨いていくことが重要
→第2領域の活用。日々の習慣が大きな違いを生む。
■今後に向けて■
●相手の話に本気で向き合うために準備をすること
→事前に想定をする習慣を大切に。
→日々の経験を次に生かす。
●相乗効果を発揮するために、「お互いに」主体性を発揮すること
→受験というプロジェクトを良い形で終わらせるために、
生徒・講師が主体性を発揮することはもちろん、
ご家庭にもその役割を担っていただくことが重要
●肉体のメンテナンスをはじめ、日々の習慣を大事にすること。
■研修講師(森口敦)へのメッセージ ■
相手を理解することは、できているようでまだまだできていないことがあると感じました。
生徒に対して伝えているように、自分自身も毎回の経験を次に生かしていきたいと思います。
本日もありがとうございました。
2/10 川瀬
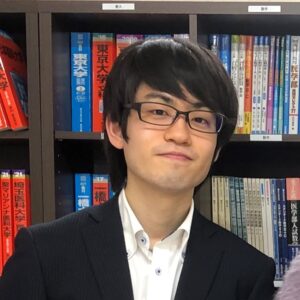
川瀬 響
2025年01月10日
■研修を受けて■
●第2の習慣「目的をもって始める」
・リーダーシップの重要性
→目的・ゴールを意識しないと、スピーディに失敗する
・真面目な人ほど、マネジメントにばかり目が行き、その目的を考えない、ということが起こりうる。
※マネジメントそのものは重要。ただし、リーダーシップを発揮できないと、マネジメントが意味をなさない。
・リーダーシップは、独断で決めることとは違う。目的を決めること。そのためにチームメンバーの力を借りることは間違いではない。(むしろ、その方がチームで動きやすい。)
●第3の習慣「重要事項を優先する」
・重要度が高く緊急度の低い「第2領域」を大きくすることが重要
→Why?:先手を打ち、自身の理念を実現するため
→How?:主体性を持つこと、スケジュール管理を大事にすること
●第4の習慣「Win-Winを目指す」
・Win-Winの関係を目指すことは当然として、お互いにWin-Winとなっていることを確認することも大事。
・Lose-Winとなっているとき、相手がそもそも「相手に不利益を生じさせている」と気づかれていないこともある。
→お互いに悩みや問題を誠実に相談することが重要
■今後に向けて■
●リーダーシップを大事にする
→常に目的・ゴールを意識する。
何のために授業するのか、何のために褒めるのか、何のために厳しいことを言うのか...。説明できる状態でいること。
●毎月大事にしたいこと・すべきことを言語化する
→プロジェクト年間計画・手帳の活用
→その時間をスケジューリングすること
■研修講師(森口敦)へのメッセージ ■
リーダーシップを発揮できるように、日々の経験を確実に自分の糧にしていきたいと感じました。
本日もありがとうございました。
1/10 川瀬
当たり前のことを実践し続ける。それこそがリーダーの近道。 主体性を発揮する。 目的をもって始める。 重要事項を優先する。 この当たり前のことを、『7つの習慣』をもとに深掘りしていきます。 評論家ではなく、我がこととして取り組むメンバーのための研修です。
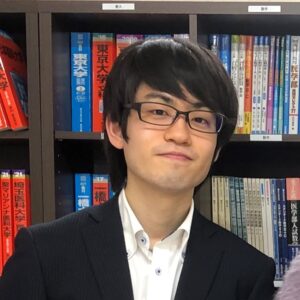
川瀬 響
2024年12月10日
■研修を受けて■
●パラダイムシフト
・結果に対して行動を変えようとするだけでなく、そもそものニーズを把握し、本質にアプローチする。
→そもそも正しく物事を見ることができているかを疑う・考える
●「依存」・「自立/自律」・「相互協力/相乗効果」
・チームを発展させていく段階では、自立/自立、相互協力ができるメンバーを集めていくことが重要(良い悪いではなく、段階に応じて選択すること)
●インサイドアウト
・物事に対して、他人や環境など周りのせいにしがちだが、そうではなく、自分自身ができることから実行していく。その結果、周囲の人を巻き込み、結果的に物事を変えていくことができる。
●主体性を発揮する(第1の習慣)
・刺激に対して、ただ反応するのではなく、選択する自由を持ったうえで反応することが重要
→特に緊急事態では重要になる。
■今後に向けて■
・どうあるべきか(理念)、を考える。(生徒にどうなってほしいのか。社会に出てどういう存在になってほしいのか。)
・理念に基づいて、メンバーを巻き込みながら行動していくことを大切にする
・何かが起こった時に、理念に基づいて、どうすべきかを考える。また、そもそも想定外のことが起こらないように、事前に準備していくことを大事にする。
■研修講師(森口敦)へのメッセージ ■
主体的に行動できるように、自分自身がどうしたいのかを考える習慣を、改めて大事にしたいと思います。
本日もありがとうございました。
12/10 川瀬
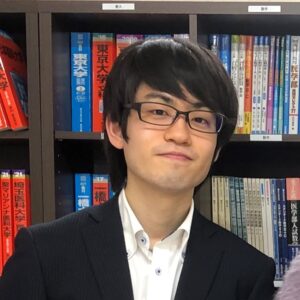
川瀬 響
2024年11月10日
■研修を受けて■
アサーティブコミュニケーション
●コミュニケーションには4つの型がある
→アサーティブ・アグレッシブ・パッシブ(受身・作為)
→相手の思いを尊重しつつ、自分の意見を主張していくのがアサーティブコミュニケーション
●アサーティブコミュニケーションの柱・姿勢・方法
→4つの柱(誠実・率直・対等・自己責任)
→7つの基本姿勢
→DESC法(Describe,Express,Specify,Consequences)
●提案を考える上でのpoint 発想の転換
→思い込みを排除する。
『こうではいけない』『こうあるべき』に対して、本当にそうだろうか、と考える。
■今後に向けて■
●アサーティブコミュニケーションのポイントを頭に入れ、活用できる状態にする
●結果を伝える点を意識『~していただけると嬉しい』
■研修講師(森口敦)へのメッセージ ■
アサーティブコミュニケーションは、
実践するところまでが難しいと感じます。
トレーニングしていきたいと思います。
本日もありがとうございました。
11/10 川瀬
「メラビアンの法則」や「真実の瞬間」と向合い、各メンバー自身がブランド形成の重要要素であることを自覚していきます。 「目配り」「気配り」「心配り」の各段階を理解し、「マナー」「サービス」「ホスピタリティ」「おもてなし」の違いについて研究。 「マニュアル」「サービス」を理解・実践するのは当然。 「ホスピタリティ」「おもてなし」を顧客・メンバーに提供したいリーダーのための研修です。
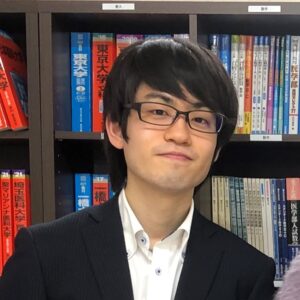
川瀬 響
2024年10月10日
■研修を受けて■
●挨拶の重要性
・挨拶は、相手に対して「チームとして動いていく」準備ができているということを伝える役割をもつ。
※挨拶ができないということは、自分をコントロールする力を持っていないと伝えてしまっているようなもの。
●人の第一印象は6秒で決まる
・人の第一印象は6秒で決まってしまう
→相手の印象を6秒で決めないように気を付ける。自分自身は、6秒で第一印象が決まると考えて、普段の行動・身なりを整えることを意識する。(清潔感)
●組織・サービスへの印象はサービスに接した15秒で決まる
・自分が顧客に対して丁寧に対応しないだけで、チーム全体のサービスに悪い印象を抱かせてしまう。
→相手への目配り・気配り・心配りを踏まえて、適切に対応することが重要。
●マナー・サービス・ホスピタリティ・おもてなしの違い
・それぞれの役割を踏まえ、今自分たちの価値提供がどの領域に属しているかを判断できるようにすることが重要(チームとして進化していくために。)
■今後に向けて■
・生徒・保護者に対して、「この塾で頑張りたい!」と思ってもらえるかどうかは、授業の質だけでなく、挨拶・コミュニケーションの仕方などのマナーも重要になることを再確認できた。
目配り・気配り・心配りを踏まえて、適切な応対をできるように腕を磨いていく。
・まずは目配り・気配りを大事にする。「きっとこうだろう」だけで判断しない。相手の状況を正しく把握することを意識する。
・そのうえで、表面的に対応するだけでなく、今何が一番大切なのかを考え(心配り)、対応していく。
■研修講師(森口敦)および川瀬リーダーへのメッセージ ■
マナーを大切にするということは、人としてとても大切なことだと感じます。まずは自分自身が腕を磨きつつ、生徒にも大切だと思ってもらえるように指導に当たっていきたいと感じました。
本日もありがとうございました。
10/10 川瀬
人は何に対して導かれるのか、そのメカニズムについて体系的に研究。①パワー理論②信頼残高③影響力の武器 自分の欲求で相手に働きかけるのではなく、相…
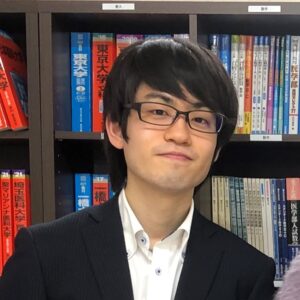
川瀬 響
2024年09月10日
■研修を受けて■
・影響力の武器
→返報性、コミットメントと一貫性、社会的証明、好意、権威、希少性
それぞれの要素に人が影響を受けやすいことを認識しながら、うまく活用していくことが重要
★相手の顕在ニーズ、潜在ニーズにアプローチすることが必須
★顧客側としても、影響力の武器を認識するだけでなく、影響力の武器を活用している場面に遭遇した際に「うわべだけだ」と表面的に判断せずに、本質を見ることが重要。
★それぞれに負の側面があることも認識し、どう対応していくかを考えることも重要。
■今後に向けて■
・コミットメントと一貫性の活用
→生徒自身が決めること、宣言すること、それを大切にすること(入会、Gmap-c、年間計画、志望校リサーチ...)
・希少性の活用
→生徒自身が「やらなくちゃ!」と思えるような設計をすること
■研修講師(森口敦)へのメッセージ ■
影響力の武器を大切にしつつ、見せかけだけにならないように、内面も磨いていきたいと思います。
本日もありがとうございました。
9/10 川瀬
人は何に対して導かれるのか、そのメカニズムについて体系的に研究。①パワー理論②信頼残高③影響力の武器 自分の欲求で相手に働きかけるのではなく、相…
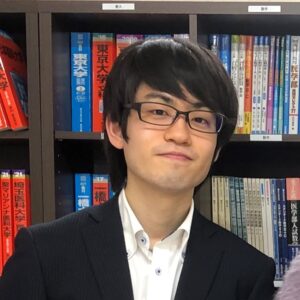
川瀬 響
2024年08月10日
■研修を受けて■
●リーダーシップパワー理論
・①専門性 ②人間的魅力 ③情報力 ④社会的地位 ⑤人脈 ⑥報酬 ⑦懲罰
・人は『自分の欲求に応じて』相手から影響を受ける
・相手に影響を及ぼす際、自分の欲求に従って相手に影響を及ぼそうとしてしまう。相手の欲求と齟齬があると、影響力を及ぼせなくなってしまう。
●信頼残高
・相手との信頼関係がどうなっているかは、自分の行動を振り返ることで判断できる
・信頼を積み重ねるためには、約束を守ることが重要。約束を設定し、守り続けることで、信頼残高をコントロールすることができるようになる。
●影響力の武器
・返報性、コミットメントと一貫性、社会的証明、好意、権威、希少性
・ニーズに応えるサービスを提供していくことが前提で、これらの武器を活用することで影響力を及ぼすことができる
・自社のサービスを説得力のある形で紹介することは、サービスを提供するものの義務
・特に、教育機関において、返報性はカギになる
■今後に向けて■
・報酬、懲罰といった影響力を使いこなせるようになること
・影響力のステージを上げていくこと
・約束を設定し、守ること。約束を守っているということを言葉にして伝えていくこと
・生徒に対して伝える『どうあるべきか』という存在に、自分自身がなれるように努力すること
■研修講師(森口敦)へのメッセージ ■
チームで、影響力の武器を使いこなしていくことの重要性を再確認することができました。
本日もありがとうございました。
8/10 川瀬
プロジェクトマネジメントを機能させる土台となるのが『理念のマネジメント』 プロのリーダーは、「権威のマネジメント」を避け、「理念のマネジメント」を構築し、維持し続ける。 「好き・嫌い」や「多数決」ではなく、説得力ある提案を互いに尊重する文化を構築したいリーダーのための研修です。
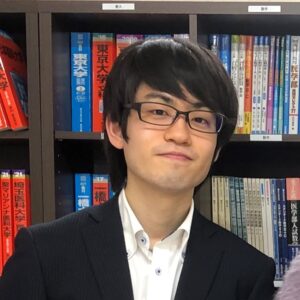
川瀬 響
2024年07月10日
■研修を受けて■
●理念のマネジメントと権威のマネジメント
・理念のマネジメント:「説得力のある意見」に従うこと
・権威のマネジメント:「好きな人・自分の意見を聞いてくれる人」に従うこと
●教育機関としての生徒・保護者との向き合い方
・私的なSNSの繋がりをしないこと
・授業外での面会をしないこと
・私的なプレゼントを受け取らないこと
→プロ意識を持って対応していくことが重要
(ルールを大事にすることは当然だが、生徒・保護者に対して説得力をもった対応をしていくことが重要)
■今後に向けて■
・理念のマネジメントの実践
→常に理念を大事にすること。情報をあるべきところに共有すること。(情報を止めない。)
・生徒・保護者との関わり方
→プロ意識を持って対応していくこと。
■研修講師(森口敦)へのメッセージ ■
ニュースなどで、教職員・塾講師の不祥事を見るたびに、
自分自身がそういうことをしないか不安になります。
少なくとも、その不安は忘れないように行動していきたいと思います。
本日もありがとうございました。
7/10 川瀬
復習回数を闇雲に増やしたり、ノートいっぱいに何度も書かせる記憶法は、社会に出てから通用しない。 多忙なリーダーは、重要事項を一発で覚える。 たとえそれができなくても、復習回数を最小限にし、効果的・効率的に記憶することが大切。
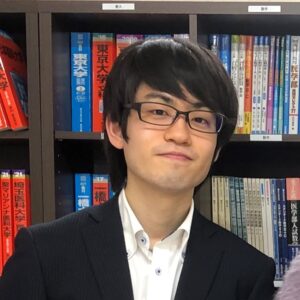
川瀬 響
2024年06月10日
■研修を受けて■
●感覚記憶、短期記憶、長期記憶
→扁桃体から繰り返し刺激が入ることで、記憶が固定化される
→扁桃体を刺激するためには、「主体性、楽しむこと、繰り返し」が重要になる。
→いかに重要性を理解できるか・させられるか
●長期記憶の分類
→エピソード記憶、意味記憶、手続き記憶
→「説明の仕方」「具体例と結び付けて意味を理解させる」といったことが重要
●忘却曲線
→インプットしたタイミングでアウトプットの回数を増やしていくことが重要。(インプットしてから時間が経つと、再び記憶を定着させるための労力が大きくなってしまう)
●シナプスの可塑性
→扁桃体から刺激が入ることで、シナプスが増強される
→記憶が定着してから時間を空けることで、シナプスが刈り込まれ、記憶が構造化される:「時間が経つと、不思議と理解できた!」という感覚
●睡眠
→レム睡眠の間に記憶が定着する。
→6時間以上睡眠を取ることが重要。
■今後に向けて■
●短期記憶に結びつける指導
→退屈な説明はしない。
→余計な情報を伝えない。必要な情報を絞り込む。
●長期記憶に結びつける指導
→目的・重要性を意識する
→具体的なエピソードと結びつける
→早め早めの年間計画。入試直前に範囲を終えると、記憶の整理ができない。
■研修講師(森口敦)へのメッセージ ■
知識を定着してもらうためにも、退屈な説明をしないように、自分自身も腕を磨いていきたいと思います。
まだまだ成長できる余地があると感じました。
本日も、ありがとうございました。
6/10 川瀬
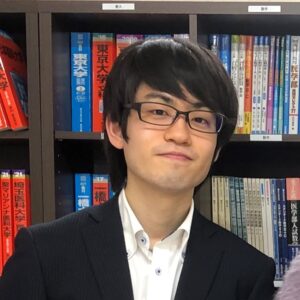
川瀬 響
2024年05月10日
■研修を受けて■
●マスマーケティングとOneToOneマーケティングの違い
→市場シェアを広げるか、顧客内シェアを広げるか
●OneToOneマーケティングを構成する5つの要素
→顧客内シェア、顧客識別、カスタマイゼーション、学習関係、LTV
●LifeTimeValueとは
→長い視点で顧客との付き合いを考えること。
エントリー顧客に対しても、将来価値を提供していけるように、丁寧にサービスを提供していく。
●Cost Of Poor Quality
→1つのミスが、大きな損失を生む。自分の1つの行動がどれだけの影響を及ぼすか想像力を持つことが重要。
■今後に向けて■
●個別指導塾は、形態としてはOneToOneマーケティングの要素が多い。
→特に、適切な学習関係を築いていくことが重要だと感じた。相手の潜在ニーズにアプローチできるかどうかが、選んでもらえる塾になれるかどうかの分かれ目になる。
→他の塾では得られない学びを得られるように。(学科だけでなく、計画を立てる・ルールを大切にする、など。あるいは、学科の内容にしても、「分かる」ではなくて「定着する・できる!」という状態にこだわること)
■研修講師(森口敦)・川瀬リーダーへのメッセージ ■
マーケティングは、売り上げの構造を考えることですが、(それもとても大切ですが、)つまりどれだけ価値を提供できるかを考えることでもある、と改めて感じました。
目の前の生徒・保護者に対して、感動してもらえるサービスを提供できるように、日々の授業準備含めて腕を磨いていきたいと思います。
本日もありがとうございました!
まだ記事がありません
人が自ら動きたくなる組織には、「信頼」「理解」「成長支援」の3つの要素があります。 本研修では、マグレガーのXY理論・マズローの欲求5段階・コーチングの領域モデルを用いて、 「人はなぜ動くのか」「どうすれば自ら動くようになるのか」を、実例を交えて深く学びます。 単なる知識の習得にとどまらず、現場で直面する課題(メンバーの停滞・生徒の伸び悩み・顧客対応の難航など)を、“人間理解”を通して紐解く実践型のプログラムです。
人が自ら動きたくなる組織には、「信頼」「理解」「成長支援」の3つの要素があります。 本研修では、マグレガーのXY理論・マズローの欲求5段階・コーチングの領域モデルを用いて、 「人はなぜ動くのか」「どうすれば自ら動くようになるのか」を、実例を交えて深く学びます。 単なる知識の習得にとどまらず、現場で直面する課題(メンバーの停滞・生徒の伸び悩み・顧客対応の難航など)を、“人間理解”を通して紐解く実践型のプログラムです。
玉井 人生100年時代といわれる今、私たちが「自身にとって最もよい人生を送る」ためには、健康や医療に関する情報を正しく判断し、適切な選択や行動を…
人が自ら動きたくなる組織には、「信頼」「理解」「成長支援」の3つの要素があります。 本研修では、マグレガーのXY理論・マズローの欲求5段階・コーチングの領域モデルを用いて、 「人はなぜ動くのか」「どうすれば自ら動くようになるのか」を、実例を交えて深く学びます。 単なる知識の習得にとどまらず、現場で直面する課題(メンバーの停滞・生徒の伸び悩み・顧客対応の難航など)を、“人間理解”を通して紐解く実践型のプログラムです。
コンサルタント・コーチ・メンター、政治家・医師・経営者、そしてチームリーダー。A&PROが関わる相手の多くが、自らの存在や組織をブランド…
この記事がNewsPicksの【キャリア・教育】【注目のトピックス記事】で紹介され、話題になっています。 本記事は、渾身の企画やメッセージがなぜ…
『責任を持つ』とは、起こりうることを想定し、想定外にも対応できる状態でいること。メンバーと顧客の生命を、机上の空論でなく、本気で守るリーダのため…
理論や蓄積されたノウハウ、他者の意見を取り入れず、自分のこれまでの経験や能力に頼りすぎて、失敗した経験はないでしょうか。自己流を脱却し、周囲を巻き込みながら組織の成果に貢献する方法をお伝えします。
責任・権限・義務。 言葉だけを知っていても意味がない。 責任・権限・義務の違いと互いの関係 報告・連絡・相談の違いと「判断・決断」との関係 報告・連絡・相談のタイミングと「マネジメント・人材育成」の関係 これらを理解し、効果的に使い分けることが重要。 理屈と機能を理解し、チームワークを大きく向上したいリーダーのための研修です。
感謝は大事だと分かっているけれど、感謝を後回しにしてしまう。そんな方に、感謝の価値を改めて実感していただき、実践するための準備となるメッセージになればと思います。
コンサルタント・コーチ・メンター、政治家・医師・経営者、そしてチームリーダー。A&PROが関わる相手の多くが、自らの存在や組織をブランド…
人間力・仕事力を高めるWEB chichiの、「地球上で最も必死に考えている人にアイデアの神様は降りてくる」<ジャングリア沖縄の仕掛け人・森岡毅…
復習回数を闇雲に増やしたり、ノートいっぱいに何度も書かせる記憶法は、社会に出てから通用しない。 多忙なリーダーは、重要事項を一発で覚える。 たとえそれができなくても、復習回数を最小限にし、効果的・効率的に記憶することが大切。
窪田:中室先生はご著書『科学的根拠(エビデンス)で子育て』の中で、エビデンスを重視した教育の必要性を説いていらっしゃいます。そもそも金融業界にい…
クレド7.好奇心旺盛、常に学ぶ。 我々の活動における身近な事柄に興味を持ち、深く学ぶ事を大切にしていきます。教え上手は当たり前、学び上手であれ。…
コンサルタント・コーチ・メンター、政治家・医師・経営者、そしてチームリーダー。A&PROが関わる相手の多くが無形サービスを中心に活躍して…
コンサルタント・コーチ・メンター、政治家・医師・経営者、そしてチームリーダー。A&PROが関わる相手の多くが無形サービスを中心に活躍して…
顧客に新しい価値を創造し続けるためには自らの脅威と向き合い、あえて自社の優位性を覆していくようなサービス・プロダクト開発が必要です。
知識として体系化されているプロジェクトマネジメント。 ただし、頭で理解していても習慣化できていないと、顧客やステークホルダーの期待値とは程遠い『自己満足なプロジェクト』となってしまう。
組織で仕事をする上で社員や従業員に必要なものとされている「当事者意識」。当事者意識とは、どのようなもので、どうすれば高めることができるのでしょう…
新規登録
アカウントをお持ちの場合はログインする
川瀬 響